1.本県肉用牛の動向
(1)飼養戸数は、全国的に減少で推移しており、本県の場合も平成4年の370戸をピークに小規模経営を中心に減少し、平成17年2月1日現在の肉用牛飼養状況は、農林統計(農水省)によると、飼養戸数は117戸で前年に比べ19戸(13.9%)と減少した。飼養頭数は平成6年の7,590頭をピークに減少傾向で推移している。平成16年に580頭増加したが、平成17年には5,360頭と前年に比べ870頭(13.9%)減少した。1戸当たりの飼養頭数は、45..8頭で、前年と同様で推移している。(表-1)(2)肉用牛飼養構成割合は肉専用種の子取用雌牛360頭で、前年比85.7%、肥育牛は1,460頭で、前年比77.2%であった。交雑種は3,150頭で、前年比86.5%、乳用種は280頭で、前年比140%であった。肉専用種の子取用雌牛の頭数は平成6年の1,010頭をピークにその後は減少で推移している。肉専肥育牛は、平成6年の1,890頭をピークにその後減少で推移している。交雑種は、平成3年以降大幅な増加が続いていたが、平成12年の4,550頭をピークに国内でBSEが発生した平成13年から減少傾向である。乳用種については交雑種の増加に伴い減少が続いている。(表-1)
(3)肉用子牛(素畜)の取引価格は、農畜産業振興機構によれば、平成17年度平均で、黒毛和種雄が522千円、前年比105.7%、黒毛和種雌が447千円、前年比107.2%、交雑種雄が286千円、前年比110.4%、乳用種雄が99千円で、前年比150%であった。
交雑種初生牛は143千円で前年比124.3%、乳用種初生牛は40千円で前年と同様であった。(表-2)
神奈川県家畜市場においては交雑種初生牛・乳用種初生牛込みで107千円、前年比112.6%あった。全品種とも全国的に高値が続いている。
(4)
枝肉の規格別卸売価格は、農水省食肉統計、東京食肉市場調査では、黒毛和種去勢A5規格は2,451円/㎏、前年比103.4%で、BSE発生前の12年度と比較すると102.0%減であった。去勢和牛のうち高品質のA5規格は、8年度に下げ止まり、以降概ね堅調に推移してきたが、BSEの発生した13年度に大幅に低下した。その後、回復傾向で推移し、平成12年度対比102.0%でBSE発生前の水準まで回復したといえる。A4規格では10年度以降低下傾向で推移し、13年度に大幅に低下した後には上昇傾向で、BSE発生前の平成12年度対比116.1%である。中級規格は、7年度に下げ止まり、7年度、9年度と堅調に推移したが、10年度以降低下傾向で推移し、13年度に大幅に低下した後には上昇傾向で、平成12年度対比132.1%とBSE発生前の水準を大幅に上回っている。交雑種去勢B3は1,508円/㎏、前年比106.3%、BSE発生前の12年度と比較すると122.0%の大幅増であった。乳用種去勢B2は846円/㎏、前年比105.1%、BSE発生前の12年度と比較すると108.3%であった。黒毛和種去勢、交雑種去勢、乳用種去勢のいずれも13年度にはBSE発生の影響で枝肉卸売価格は暴落したが、各品種とも回復したといえる。黒毛和種のスソ物、交雑種及び乳用種の価格上昇は平成15年12月のアメリカからの輸入禁止措置による影響が考えられる。(表-3)
横浜食肉市場調査においてはバブル崩壊後の不景気で各品種とも枝肉価格の下落が平成8年度まで続き、平成9年度以降徐々に回復傾向にあったが、平成13年度にはBSEの発生により枝肉価格は暴落した。平成14年度以降徐々に回復し平成17年度にはBSE発生前の水準を上回っている。黒毛和種去勢の枝肉格付等級5では平成10年度以降、2,300円/㎏台で堅調に推移してきたが、平成13年度には1,998円/kgと大幅に下がった。平成17年度は2,461円/㎏で前年比102.1%となっており、平成12年度と比較すると106.9%と12年度を上回っている。(図1-1)
 |
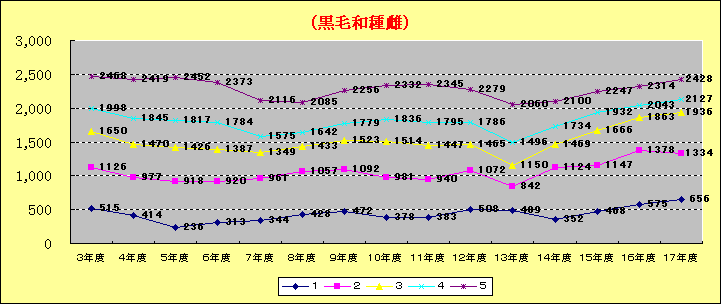 |
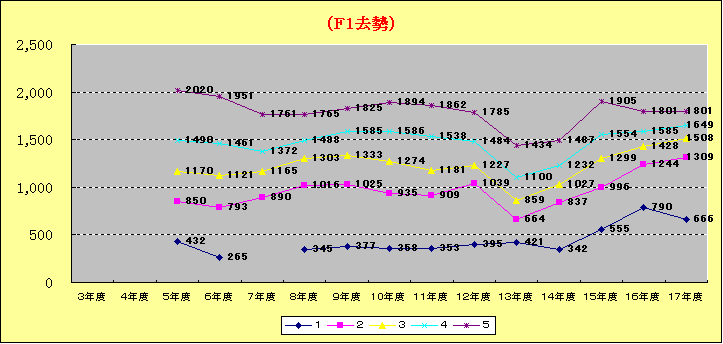 |
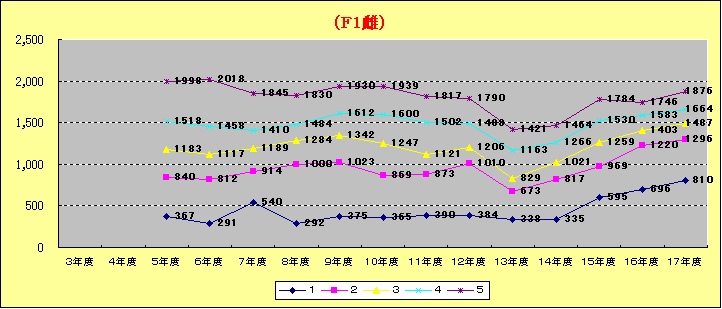 |
2.診断農家成績の分析概要
平成17年度畜産経営技術高度化促進事業において肉用牛部門は、経営診断に基づく改善指導5戸、経営管理技術指導2戸、生産技術指導3戸、フォローアップ指導10戸の計20戸に対して支援指導を実施した。このうち経営数値の明らかな5戸の事例について概要を述べる。(1)診断農家の飼養規模(表-4)
ア.経営形態
経営形態は様々で、肥育部門に繁殖和牛の一貫生産を取り入れている経営が3事例、肥育専門経営が2事例であった。肥育部門において、黒毛和種の肥育専門経営が4事例、黒毛和種と交雑種の混合肥育経営が1事例であった。
イ.飼養規模
飼養規模については、労働員数1人当りでは、肥育牛50頭以上が1事例、50頭未満が4事例であった。実頭数では、肥育牛50頭未満が2事例、50頭以上100頭未満が2事例、100頭以上が1事例であった。(2)肥育成績
5事例の出荷牛の個体別成績について品種及び肥育タイプ別に分類し比較する。1)黒毛和種去勢若齢肥育牛(表-5)
ア.肥育もと牛の導入
飼養開始日齢は、最大が292日、最小が8日、平均282.3日で、前年度平均の275.9日を上回っている。ET和子牛を早期で導入している1号農家を除いた飼養開始日齢は307.1日で前年度の287.8日を上回った。飼養開始体重は、最大が316㎏、最小が30㎏で平均298.6㎏と前年度平均の285.4㎏を上回っている。1号農家を除いた数値は、324.3㎏で前年度の296.5㎏を上回っている。また、先進的畜産経営(平成17年調査結果(社)中央畜産会調査(以下、先進事例))の283㎏を41.3㎏も上回っている。
素牛導入価格は、517千円から80千円で、平均492千円で、前年度平均の462千円を上回った。1号農家を除いた数値は533千円で、前年度の479千円を大幅に上回っている。 更に、各経営の自家産牛を除いた外部導入牛の平均価格は556千円で、前年度平均の494千円を上回っている。また、先進事例の438千円を大幅に上回っている。
イ.出荷状況
出荷日齢の各経営における平均は最大995日から最小798日、平均947.0日で、前年度平均の939.8日を若干上回った。飼養日数は最大790日から最小627日、平均664.8日で、前年度平均の664.3日と同様で、先進事例の614日を大きく上回っている。
出荷体重は最大806㎏から最小472㎏と差がみられ、平均771.3㎏で、前年度平均761㎏を上回り、先進事例の730.6㎏も大幅に上回っている。
枝肉重量は最大532㎏から最小328㎏と幅があり、平均509㎏で、前年度平均の502㎏を上回り、先進事例の467.5㎏を大幅に上回っている。
1日1頭当たり増体重(DG)は最大0.788㎏、最小0.559㎏、平均0.712㎏で、前年度平均0.716㎏を下回り、先進事例の0.73㎏も下回った。
販売価格は出荷牛1頭当たり最大1,438千円から最小507千円、平均1,297千円で、前年度平均1,217千円を上回った。また、先進事例の957千円を340千円も上回っている。
枝肉単価については最大2,785円/㎏から最小1,545円/㎏、平均2,542円/㎏で、前年度平均の2,419円/㎏を上回った。また、先進事例の2,049円/㎏を601円も上回っている。
全体的に出荷日齢が若干増加したものの、肥育日数は横ばいで、更に1日1頭当たり増体重(DG)がやや減少している。導入体重が増加した分、出荷体重が増加したといえる。
上物率が伸びたことと、枝肉相場も手伝って枝肉単価は大幅に増加し、出荷体重も増加していることから今年度の平均販売価格も大幅に伸びた。
2)黒毛和種雌若齢肥育牛(表-5)
ア.肥育もと牛の導入
飼養開始日齢は、最大426日から最小39日、平均240.4日で、前年度平均213日より27.4日増加した。導入日齢の早い1号農家を除いた平均は364.3日で、同様に1号農家を除いた前年度平均304日を60.3日も上回った。飼養開始体重は、最大400㎏から最小54㎏、平均236.9㎏で前年度平均214.2㎏を上回った。導入日齢の早い1号農家を除いた平均は352.7㎏で前年度平均298.3㎏を上回った。
素牛導入価格は、自家産牛の評価額を含むと最大428千円から最小102千円、平均234千円で前年度平均の大きく175千円を上回った。
イ.出荷状況
各経営の出荷日齢は最大1,030日から最小818日、平均863.1日で、前年度の平均922.4日と比較すると59.3日減少している。飼養日数は780日から537日、平均623.1日で、前年度平均709日を下回った。導入月齢が早い1号農家を除いた平均は661.5日で前年度平均668.2日と比較すると6.7日短縮した。
出荷体重は最大698㎏から最小527㎏、平均636.5㎏で、前年度平均643.3㎏を下回った。枝肉重量については最大459㎏から最小367㎏、平均425.8㎏で、前年度平均427㎏を下回った。 1日1頭当たり増体重(DG)は最大0.711㎏、最小0.492㎏、平均0.646㎏で、前年度平均0.604㎏を上回った。
販売価格は出荷牛1頭当たり最大1,158千円から最小712千円と格差がみられた。平均967千円で、前年度平均911千円を上回った。
枝肉単価は最大2,549円/㎏から最小1,942円/㎏、平均2,258円/㎏で、前年度平均の2,099円/㎏を上回っている。
全体的に、DGが増加したが、肥育日数の短縮がみられ、出荷体重の減少したが、枝肉単価の増加によって平均販売価格が大幅に伸びている。
(3)経営成果(表-7)
ア.費 用
家族労働費を除いた総費用の各項目の割合は素畜費が45.4%、購入飼料費が28.0%、償却費が4.3%、その他一次生産費が9.6%、販売一般管理費及び営業外費用が12.7%で、素畜費と購入飼料費を合わせると73.4%と総費用の大部分を占めていおり、前年度の73.1%を若干上回った。(図2)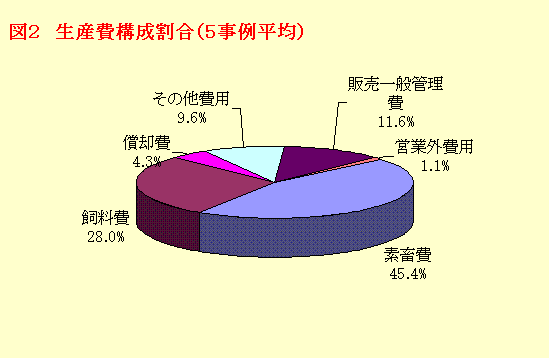
購入飼料費については最小が136千円、最大が233千円と差がみられた。平均は165千円で前年の165千円と同様に推移した。
その他の一次生産費を合わせた当期生産費用の合計でも経営間格差がみられ、最小が453千円、最大が582千円と129千円の差がみられた。平均は513千円で前年の483千円を上回った。
生産原価については最小402千円から最大499千円、平均は458千円で前年の410千円を上回った。
イ.収 益
肥育牛1頭当たりの肥育牛販売収入は最小の269千円から最大の818千円と大きな格差がみられた。平均は627千円で前年の562千円を上回った。堆肥販売収入のある経営は4事例で肥育牛1頭当たり最小の13,422円から最大の30,462円で、平均は13,680円で前年の15,206円を下回った。
売上高の合計は最小537千円から最大823千円、平均688千円で、前年の599千円を大幅に上回った。
ウ.所 得
肥育牛1頭当たりの所得は74,645円から209,305円と大幅な格差がみられた。平均は148,630円で、前年の122,102円を上回った。1号農家の除く2号、3号、4号、5号農家において先進事例の肉用種若齢肥育の所得106,627円を上回っている。所得率は13.88%から25.40%、平均が21.59%で、前年の20.36%を上回り、1号農家の除く2号、3号、4号、5号農家において先進事例の肉用種若齢肥育の所得率18.3%を大きく上回っている。
(4)生産性・収益性分析
出荷牛の販売価格から素牛価格を差し引いた増加額と、さらに出荷までに要した飼料費を差し引いた肥育差益について品種別に検討する。1)黒毛和種肥育(去勢・雌)(表-8)
4等級以上の格付率は33.3%から90.6%と大幅な格差がみられ、平均は74.3%で、前年度66.9%を上回った。枝肉重量は、349.8㎏から512.7㎏と格差があり平均498.9㎏で前年度494.7㎏を若干上回った。3号、4号、5号農家は去勢・雌の平均で県指標の500㎏以上を達成している。年度ごとの平均値の推移をみても年々大型化が進んでいることがわかる。
出荷日齢は809.1日から971.3日で、平均は938.7日、前年度平均938.1日と横ばいであった。 素牛価格は92千円から512千円で、平均466千円と前年度434千円を上回った。黒毛和種のET子牛を酪農家との契約によって早期導入している1号農家を除いた素牛価格は519千円であった。
飼料費は243千円から317千円で、平均は267千円と前年度270千円を若干下回っている。 1日1頭当り増加額は675円から1,460円と幅があり、平均1,218円で前年度平均1,132円を上回り、先進事例の845円を大きく上回った。
1日1頭当り肥育差益についても338円から1,072円と幅があり、平均813円で前年度平均726円を上回っている。
素牛価格の増加があったが、飼料費が横ばいで、販売価格が前年度1,187千円から1,264千円に増加したため、増加額、肥育差益ともに前年度を上回っている。平成12年度に最も低下した増加額と肥育差益はその後、順調に増加している。
3.指導の方向と対策
以上が平成17年度の経営分析結果である。平成18年の7月に丸2年以上続いた米国産牛肉の輸入が再々開されたが、米国からの輸入量は伸びなかった。全般的に出荷頭数が少なかったことや、量販店の原産地表示などの絡みから国産、特に生産履歴の明らかな銘柄和牛や、消費者の産地志向の高まりから年間を通じて高値基調であった。年間30万トン前後の輸入量があった米国産牛肉の再々開後の輸入量が月間2000トン前後しかなく、米国産牛肉を主体に取り扱っていた外食産業(焼き肉レストラン等)が国産にシフトしたことも国産牛肉の相場高に拍車をかけた。
17年度には枝肉相場はBSE発生前の水準を超えているが、一方で、肥育もと牛の高値も続いており、更に昨年秋以降の飼料価格の上昇が収まらず経営を圧迫している。
(1)収益性の向上
肥育もと牛の高騰、とうもろこしのエタノール利用による飼料価格の高騰の中で収益性向上のための対策を早急にとらなければならない。費用の低減としては事例にもみられるが繁殖一貫生産を取り入れることによる素畜費の低減が考えられる。しかし繁殖和牛の飼養管理の技術面や繁殖部門が軌道に乗るまでの資金の回収等難しい面もある。酪農家と連携してETや体外受精卵移植の子牛を導入する方法も考えられる。一貫生産にもいえることだが、この場合、子牛の哺育期・育成期の管理技術が課題となる。また、地域内での子牛流通体制を確立するためには行政・関係機関の協力が不可欠である。
購入飼料費の低減については、全国的にエコフィードについて注目されはじめたが、本県においては食品製造副産物の利用技術は既に定着している。肉質及び増体を目指しながらトウフ粕、ビール粕を配合飼料と混合した独自の飼料給与技術をつちかってきたが、今後、配合飼料価格上昇に対して更に研究を進め食品製造副産物の利用を推進していかなければならない。農家個々での原材料の収集が困難になってくることも予測されることから、行政・関係機関の協力が必要となってくるであろう。
販売収入の増加による収益性向上だが、枝肉重量を増やして販売価格を増加させるしかない。年々出荷体重が増加してきていることは先に述べたが、最近の食肉市場では和牛去勢でも枝肉重量500㎏以上があたりまえになっている。特に交雑種においては枝肉重量をいかに確保するかが重要な課題である。
和牛の場合、適正な価格で高品質、枝肉重量のでる肥育素牛を導入し肥育コストの節減を図ることである。生産コストを低減するには、肥育期間の短縮も重要な要素の一つであるが、肉質とのバランスを考慮しながら一日当りの増体重を向上させ、肉量・肉質をより短期間で作る技術が必要である。
(2)販売対策
今回の経営分析結果にみられるように順調に所得を伸ばしている経営も存在している。これらは高品質牛肉生産に努力し実行してきた経営である。消費者は「安全」で「安心」できる食料を求めている。家畜個体識別システムをはじめ牛トレーサビリテイシステム等、生産者、行政、畜産業界一丸となって努力して「安全」については確保している。次のステップはいかに消費者に「安心」してもらうかである。消費者は生産者の顔が見える食品を求め、地産池消のニーズが以前に増して強くなっている。これは大消費地をかかえる本県にとってチャンスでもある。規模拡大によるスケールメリットを追求できない本県においては、地元の「安全・安心」に注目した販売戦略も今後の生き残り対策の一つである。欲を言えば、もう一つレベルアップして少数精鋭で高付加価値生産を行い、「安全・安心」に「美味しい」という付加価値をプラスした銘柄牛ブランドを目指したい。