1�D�{���{�{�̓���
�@�{�Y���v�i�_���ȁj�ɂ��ƁA����17�N2��1�����݂̖{���ɂ�����̗��{�̐��{���{�͎��{�ː�89�ˁA���{�H��1,453��H�ƂȂ��Ă���A�o�c�҂̍�������蓙�Ŏ��{�ː���5%�A���{�H����3.5%�ƁA�ɂ₩�ł͂��邪�ː��A�H���Ƃ��������Ă���B�@�������A����ł͌�p�҂��炿�A�L���ȗ��n�������������āA�s�s�Ƌ�������ӗ~�I�Ȏ�g�݂��e�n�Ō����Ă���B
�@�����870��������L��������n�Ƃ����D�����ɗ��n����{�{�o�c���A�{���̒��̐헪��W�J���A�o�c�̌����}���Ă��邩��ł���B�܂��A�Ȃ��ɂ͑����̏[���ɂ��킹�āA�}�|�P�e�B���O���T�|�`��ϋɓI�ɍs���o�c���������Ă���B
�@�����́A�u�s�s�{�{�v�ƌĂ���r�I���H���̒����K�͂ł͂��邪�A��Ɖ��̌`�ԂŁA�s�s�Ƌ������Ȃ��瑽�l�Ȕ��W�����҂���Ă���B
�@�������A�S���I�Ɍ���ƁA�����̒���K�͌o�c���X�P�|�������b�g�Ŕ�����₨���Ƃ��āA���Y���̉ǐ艻���i�݁A�\���I�Ȑ��Y�ߏ�̊�ɂ��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B
�@�܂��A���H�����ł́A��x�t���𗘗p����Ɖ��i�̈����A��y�����烊�s�[�^�[�����邽�߁A�t���̗A���������X���ɂ���A�o�c�͌������ł���B
�@����17�N�x�̌{���̍������Y�ʂ́A2,481,000�g���i�O�N��99.6%�j�Ƃ��O�N����������l�ƂȂ����B�܂��A�A���ʂ͍������Y�ʂ̌�����⊮���铮���������A150,959�g���i�O�N��112.6%�j�ƁA�����̌X���ƂȂ��Ă���B
�@�܂��A�̗��p�߂��q�i�̂��t���H����109,801��H�ŁA�ΑO�N��104.6%�Ƒ����ɓ]���Ă���̂ŁA����̎����o�����X�ɒ��ӂ��K�v������B
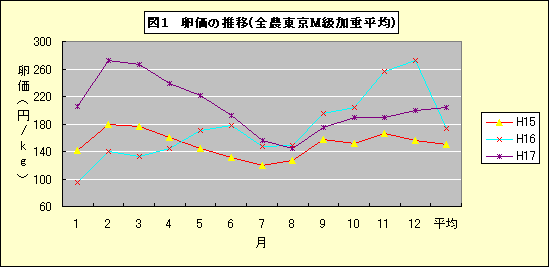
2�D�f�f�_�Ɛ��т̕��͊T�v
�i1�j�f�f�Ώیo�c�i�_�Ɓj�̊T�v
�@����17�N�x�ɂ�����{�Y�o�c���x�����i���Ƃ̑Ώۗ{�{��́A�o�c�f�f�Ɋ�Â����P�w����5�ˁA�o�c�Ǘ��Z�p�w��1�ˁA���Y�Z�p�w��4�ˁA�t�H���[�A�b�v�w��10�˂̉���20�˂ł������B�@�Ώ۔_�Ƃ̌o�c�K�͂ώ��{�H���Ŏ����ƁA�}2�̂Ƃ���ł���A2��H�䂩���10���H��ł������B���{�ɂ̌`���́A�J���{��1�ˁA���^�E�C���h�E���X�{��3�ˁA��^�E�C���h�E���X�{��1�˂ł������B
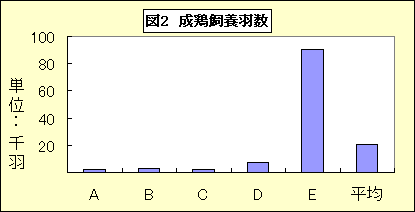
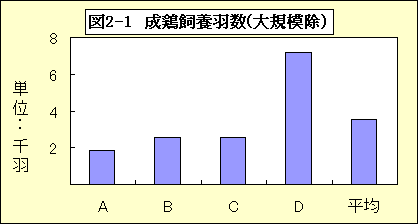
�o�c�̏펞�]���Ґ��́A3.0�`17.2�l�ł���A���K�͌o�c�ł͉Ƒ��J������̂Ƃ����`�ԂŌ����ɉc�܂�A�ٗp�J�͂̎�̂̓p�|�g�ٗp�ł������B�������A��K�͌o�c�ł͏�̌ٗp�l�����p���Ă���B
�@�o�c�`�Ԃ���݂�ƁA��ؐ��Y�ȂǂƂ̕����o�c��3�˂ŁA����2�˂͗{�{�̐�ƌo�c�ł������B������o�c�g�D����݂�ƁA�l�o�c��3�ˁA�L����Ђɂ��o�c��1�ˁA�_���g���@�l��1�˂ł������B
�i2�j�{�ݗ��p�Ɠ����J��
�A�D�{�ɂ̗��p���@�Ώیo�c�̃P�|�W���p���͐}3�Ɏ������Ƃ���A�ō���90.1%�A�Œ��51.5%�A���ς�64.7%�ƂȂ��Ă���A�w�W�l�i86�`88%�j����o�c��1�˂ł������B���Ă̓X�P�[�������b�g��Nj����ċK�͊g���i�߂Ă������A�����K�̗͂{�{�o�c�́A���̂ɂ��L���Ȕ̔��헪�ɐ�ւ������߁A�K�����{�H���ɗ}���A1�H������̌{����������߂Čo�c�����肳����X���������A���ꂪ���p����Ⴍ���Ă���v���ł���B
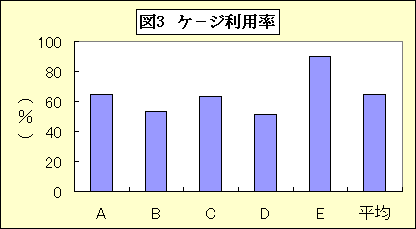
�@���{1�H����̔N�ԘJ�����Ԃ�}4�Ɏ������B�ō���1�H����3.06���ԁA�Œ��0.51���ԂŁA���̕��ϒl��1.90���ԂƂȂ��Ă��邪�A�����K�͂͑�K�͂�2�`6�{���x�̑����J�����ԂƂȂ��Ă���B�܂��A�O�N�ɔ�ׂĒ����K�͂͂�T�J�����Ԃ������Ȃ��Ă���B
�@��ʓI�ɂ́A���K�͌o�c�قǘJ�����Ԃ�������X�������邪�A����́A3�˂̏��K�͌o�c�ł͎��Ɣ̔����������A���{�Ǘ��̂��߂̋@�B�������Ȃ��A�{���̏����Ɣ̔��ɑ����̎��Ԃ������Ă��邽�߂ŁA���̕��P�H������̌{�����㍂�͍����Ȃ��Ă���B
�@���ꂩ��̎���A�J�����Ԃ̒Z�k���v������Ă���A�{�{�ɉ����Ă��u��Ƃ肠��{�{�o�c�v�̐��i���K�v�ł���B���̂��߂ɂ́A���̋@�̊��p�A�����̔����i�A�w���p�[�̍\�z����X�̌����I�ȕ������l���Ă����K�v������B
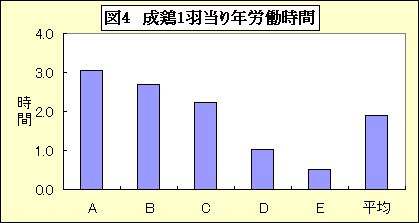
�i3�j���{�{��ƍX�V�{�̓���
�A.���{�{���@�f�f�Ώۂ̗{�{�ꂪ���{����{��i�����j�͔��F���n�Ƃ��āA�W�����A�A�W�����A���C�g�y�уV�F�|�o�|�A���F���n�Ƃ��āA�{���X�u���E���y�т��݂��iG-130�j�A���ԐF�Ƃ��Ă�����iG-360�j�����{����Ă���A��K�͌o�c�ł͔��F�n�݂̂ł��邪�A�����K�͌o�c�ł͗L�F���n����̂ɔ��F�n�����{����Ă����B
�@���̒����K�͂̌o�c�͓��ꗑ��t�����l���Ƃ��āA���̂Ŕ̔�����Ă���A���F���n�⒆�ԐF�n���������{����Ă���̂́A�ڋq�̃j�[�Y�f�������̂ł���B
�C�D�X�V�{�̓����Ƌ������H�̏�
�@�X�V�{�̓����͕\1�̂Ƃ���ł���B����2�˂͏��������A1�˂͏����y�ё吗�̌��ݓ����A����2�˂͑吗�����ł������B�܂��A�X�V�{�͔N��2��5��̓����i����3.8��j�̃��b�g�ō\������Ă����B����̕��ω�����v�ɍ��킹���{�����Y�ʂ��m�ۂ��邽�߃��b�g���͑�����̂��ʏ�ł��邪�A����͌������Ă���B���̗v���Ƃ��āA�Y�������Z�p�̓����A���C���t���G���U�ɂ�铱���̍��������l������B
�@��K�͌o�c�ł͏��Ȃ����b�g�\���ŋ������H�����{���A���K�͂̂Q�o�c�ł͋������H�Ȃ��Ŏ��{���Ă����B
| �{ �{ �� | A | B | C | D | E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | 4 | 4 | 4 | 5 | 2
| �������� | 120���� | �����A121���� | 120���� | ���� | ���� | |
�i4�j�{���̔̔�
�@�{���̎�����i�́A�_����≮�ւ̏o�ׂ̏ꍇ�́A�S�ĐV�����ꂩ��o����������������i�Ŏ������Ă���B���̎�̂̔_��ł͒��̔��A�H���E���H�ƎҁE����҂ւ̔z�B�A��z�֓���X�̌`�ԂɑΉ����Ă��邪�A���i�͔����Ɣ�����̑��Ύ���ƂȂ��Ă���B�@���̌��ʁA�f�f�Ώۗ{�{��̕��ϗ�����328�~�ƎZ�肳�ꂽ���A�{�{�ꂲ�Ƃ̕��ϔ̔�����������ƁA172����417�~�̊Ԃɂ���A�T��2.5�{�̊J�����݂�ꂽ�B
�@�V������͕���17�N1���`12���̑S�_�l�����d���ς�204.4�~�ŁA���̗����͂����ܔN�ԂŌ����Ȃ����l�̗����ł������B1���������畽�ς�200�~��̑���ƂȂ�2���A3����250�~���闑�����������B�ď��150�~�O��̑���ƂȂ������A�㔼���������A�v�X�ɔN�ԕ��ς�200�~������ƂȂ����B
�@���̂悤�ȏŁA���́i��z���܂ށj���s���Ă���{�{��4�˂̕��ς�367�~�Ƃl���d�̔{�߂����i�Ŕ̔����Ă���A���̂������i�̍��l�̉��b�ō��܂ł���50�~���x�����̔������ƂȂ����B�o�c�ɂ���Ă�500�~�̗����ݒ������A�H�v�Ɠw�͎���Ŕ��ɗL���Ȍo�c�̓W�J���\�Ȃ��Ƃ����������B
�܂��A�{���̔̔��ŋ����̂�����@�Ƃ��āA�]�藑�A���ʁA�j���𗑖��Ƃ��A���i�ʂȂ��̔����Ă������������B
�@���̋�̓I��i�Ƃ��āA���̂��Ƃ���������Ă���B
�@����h�{�f���̎����Y���ɂ�鍷�ʉ��{���E�t�����l�{���̐��Y�B
�A���ĊŔ��邢�͐܂荞�ݍL���A�C���^�|�l�b�g���p���ɂ�鎩�Ɛ��Y�{���̐ϋɓI��`�y�ї��̗L�����p�Ƃ��Ĕj���A���ʓ��̉��H�i�Ⴆ�Η����j�̔��ɂ�鑝�v�B
�B�����̔��@���̒��̔��{�݂̐����A�[���B
�C�{�ɋy�ї{�{����ӂ̐��ڂƔ����ɂ�����҂̗U���B
�D�����I�ȏܖ������̐ݒ�E�\���ȂLj��S���̃A�s�|���ȂǁB
�E�_�Y���i�]��Ȃǂł̗D�G�܂̎�܌f��
�i5�j��ȋZ�p�I�w�W����̕���
�A�D�琬���Ɛ��{�����@�f�f�Ώۗ{�{��̍X�V�{�̓�������͕\1�Ɏ����Ƃ��蓯��ł͂Ȃ��̂ŁA���ڂ̔�r�͓K���łȂ����A�w�W�l�i97�`100%�j�ȏ�ŁA�ǍD�Ȑ��тł������B
�@�܂��A�ЂȈ琬�̐��ۂ͏����̐��Y�ɑ傫�����E���邱�Ƃ���A�琬���𒆐S�Ɏ��{�Ǘ��̈�w�̌��オ�]�܂��B
�@���{�ŁA�ւ����{�Ƃ��ċL�^�������̂̒��ɂ́A�����p�����ꂽ�ʌ{���܂܂�Ă���̂��ʗ�ł���̂ŁA�ւ����{�ƓK�X�����{���܂Ƃ߂đ��Ռ{�Ƃ��Ĉ����A���{�����Ƃ����T�O�ŕ���邱�ƂƂ��A���̐��т�}5�Ɏ������B�S�̕��ς�4.8���ł��������A�{�{��Ԃ̍��͑傫���A�ō��i11.4���j�ƍŒ�i0.7���j�ŁA�傫�ȍ����������B�w�W��12%�ȉ��ƂȂ��Ă��邪�A1�_��������Ďw�W��肩�Ȃ�ǂ����тł������B
�@�����������Ɛ��Y�̌������ቺ���邱�ƂɂȂ�A�琬��p�̉�����o�����ɏI��邱�ƂɂȂ�B�J���{�ɂł͐^�Ă̏��M�ɂ��ւ����A�E�C���h�E���X�{�ɂł͒�d���̓��ɂ��傫�ȑ��Ղ������N�������˂Ȃ��̂ŁA�����̎��{�Ǘ��ł̊�@�Ǘ����������Ă������Ƃ��d�v�ł���B
�C�D���{�̍X�V���Ɠ�����
�@���{�̍X�V���A��������}5�Ɏ������B�����l�Ƃ��{�{��Ԃ̍����傫���A���̗v���Ƃ��āA�������H�̎��{�ⓑ�������̍��ɂ����̂����邪�A���C���t���G���U�̉e���Ōo�c�ɑ���s���ɋ���A���������A�̗���ɂ����̂�����B
�@�������H�����{����A���{�̋��p���Ԃ������Ȃ邩��A���R�A�����E�X�V�Ƃ��Ⴍ�Ȃ�B
�@�܂��A�K�X�����̏ꍇ�́A���{�̋��p���Ԃ������ɘj��ꍇ�������A�����E�X�V���ቺ�̗v���ƂȂ�B�X�V���̑S�̕��ς�86.9%�ł���A�w�W�l93%���Ⴂ�l�ƂȂ��Ă���B�X�_�Ƃ̐��l��59.4%�`129.6%�Ƒ傫�ȃo���c�L�ƂȂ��Ă���B
�܂��A�������ōł����������̂�104%�ŁA�Œ��54.3%�ł���A���ς�80.9%�Ŏw�W�l�ɋ߂��l�ł������B
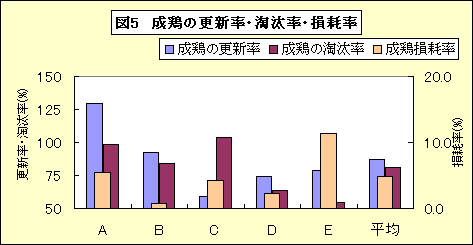
�@���{1��1�H����̎�������ʂ͐}6�Ɏ����Ƃ���ŁA����ʂ̍Œ��94.9g�A�ō���118.2g�ƁA��24g�̍��̊J��������A�S�̕��ςł�103.0g�ƂȂ������A�P�_��������Ďw�W�l�i110�`113g�j��菭�Ȃ�����ʂɂƂǂ܂����B����ɂ́A�ŋ߂̈����ǂ���������ʂ̒ጸ�ɃV�t�g����Ă���A���̌��ʂ�����Ă�����̂ƍl������B
�@��������ʂ͌{��A�Y���ʁA���^�����̉h�{�����A�{�ɂ̊������i�����A�����j�y�уG�T��̌`�ԁi�G�T���ڂ�Ɩ��ڂȊW�j���ʼne�������B�ŋ߂̈����ǂł͎�������ʂ̉��P�ɃE�G�C�g���u����Ă���A���P�͐i��ł���B�������A������͐��Y�R�X�g�ɑ傫�ȃE�G�C�g���߂�i�}13�j�̂ŁA���{�Ǘ��ł̎����ߌ��͏d�����ׂ����ڂł���B
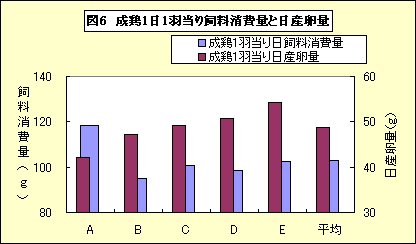
�@�}6�ɓ��Y���ʂ��Ď������B�S�̕��ς�48.7g�́A�w�W�l�i49�`51g�j�̉����l�����Ⴂ�l�ɂ�����B�_�ƊԂ�42.2�`54.3g�Ɩ�12g�Ƒ傫�ȍ��ƂȂ����B���Y���̑S�Ă����Ɣ̔����Ă���{�{��ŒႭ�A����͌{�������Ɣ̔��ʂɗ͂�����A���{�Ǘ��ʂɖڂ��͂��Ȃ��Ȃ��Ă���ƍl������B
�@�܂��A�����I�Ȍ{�����������z���ĈӐ}�I�Ȑ��Y�������Ȃ���Ă���P�[�X��������B
�I.�����v����
�@�ߔN�A�̗��{�̐��\�Ɣz�������̕i���̌���Ƃf���āA�����v�����͂��Ȃ���P���݂���B�����v�����́A1.89�`2.80�ŁA����2.11�ł������B
�@�����v�����̗ǂ��Ƃ���́A�œK�Ȍ{�ɓ����R���g���[���A�����̍��h�{���A�{��̑I���A�a���ڂ�ɒ��ӓ����傫�����f���Ă�����̂Ǝv����B
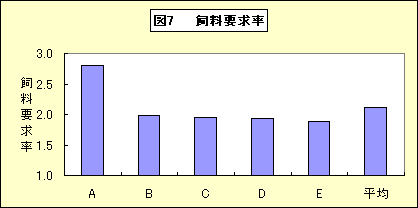
�i6�j��Ȍo�ϓI�w�W�̕���
�A�D�̔������Ɣ��㍂�@�f�f�Ώۗ{�{��̌{��1kg����̔̔������͐}8�Ɏ����悤�ɁA�{�{��Ԃɑ傫�ȍ����F�߂�ꂽ�B�ō��i417�~�j�ƍŒ�i172�~�j�ɂ�2.5�{�̊J���������Ă���A�̔����@�̈Ⴂ���o�c�헪�̌��ߎ�ł��邱�Ƃ���������Ă���B
�@���ߍׂ��Ȕ̔��ŏ���҂̑��l���ɑΏ����邱�Ƃŕt�����l��F�߂Ă��炢�A���������ێ�����悤�w�߂邱�Ƃ��̗v�ł���B
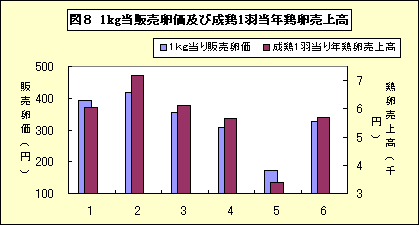
�C�D�����̍w�����i�Ɛ��{1�H����̎�����
�@�����̍w�����i�͎����A��������i����ʁA����̎x�������A�p�j�A�����E�i���ɂ���āA���R�����o��B���Ɏ���ʂƉ��i�Ƃ͕��̑��֊W�ɂ���A��ʎ���ł͊i�i�Ɉ����Ȃ�̂���ł���B
�@���̂��߁A�{�{��ԂɊr���������邱�ƂƂȂ�A���{����1kg����̉��i�́A�ō�63.1�~�A�Œ�38.1�~�A����49.7�~�ł������B�����č��ʉ��{���E�t�����l���Y���Ă���o�c�ł́A���i�������i��Ƃ��č��`�������j�̋��^��A����ȉh�{�������܂ގ�����p���邽�߁A���{����������Ȃ�X���ɂ������B
�@�����̍w�����i�͎����A��������i����ʁA����̎x�������A�p�j�A�����E�i���ɂ���āA���R�����o��B���Ɏ���ʂƉ��i�Ƃ͕��̑��֊W�ɂ���A��ʎ���ł͊i�i�ƈ����Ȃ�̂���ł���B
�@�����̊W�𐬌{1�H����N�Ԏ�����Ƃ��Đ�������ƁA�}9�̂悤�Ɏ��Ɣ̔��䗦�̍������K�͌o�c�قǍ����A�K�͂��傫���������Ƃ��Ĕ_����≮�̏o�ׂ������o�c�قLj����Ȃ��Ă���B
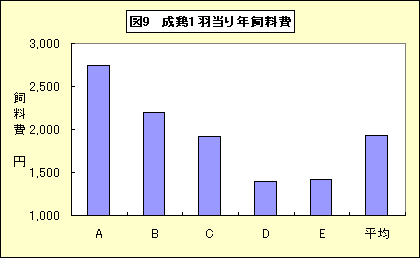
�@�N�ԏ����z�i�Ƒ��̘J����V�j�𐬌{1�H����ƁA�{�{�]����1�l����Ƃ��Đ}10�Ɏ������B���{1�H����̏����z�͍ō�3,004�~�A�Œᇙ5,347�~�ŁA���ς�673�~�ł������B���̂悤�ɁA�o�c�Ԃ̊r���ɑ����̊J�����������̂́A���{�H���A���[�e�[�V�����A������A���{�������Ɣ��㍂�Ƃ̃o�����X�̗ǔۂ��傫���֗^���Ă���B
�@�����ɂ��}8�Ɏ������̔������y�є��㍂�Ƃ̊֘A�������݂�ꂽ�B
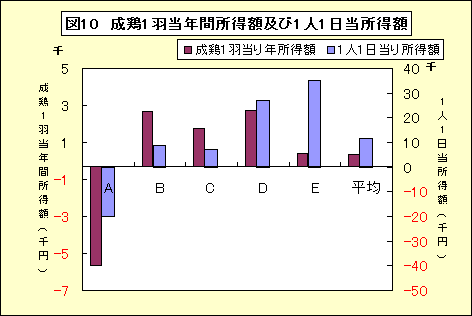
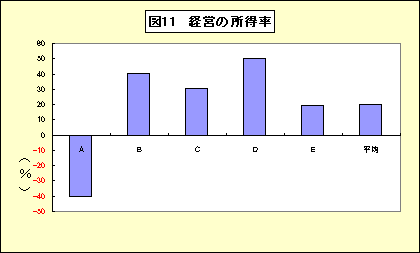
�i7�j ���Y�����̕���
�A�D�o�c��Ɛ��Y�����@�{��1kg�̌o�c��i���ƘJ���͊܂܂Ȃ��j�ƌo�c��畛�Y�������i�{�ӂ�y�єp�{���̔��p�����j�����������ċ��߂����Y�����̊W��}12�Ɏ������B���ςł͌o�c�412.2�~�A���Y������404.3�~�ƂȂ�A���̍���7.9�~�ł������B
�@�}12�̕�������_�O���t�Ԃł̍����傫���P�[�X�قǔp�{�ƌ{�ӂ�̎����������o�c�ƌ����邪�A�o�c�ɂ�蕛�Y���̔̔�����肭�����Ă���P�[�X�ƁA�w�͂��K�v�Ȍo�c�ō����o�Ă���B
�@���ɁA�ŋ߂́A�p�{�����������߂�Ⴊ���Ȃ��Ȃ�A�ނ���t�ɏ�������̂ɔp�{���������x�����Ⴊ�����Ȃ��Ă��Ă���B
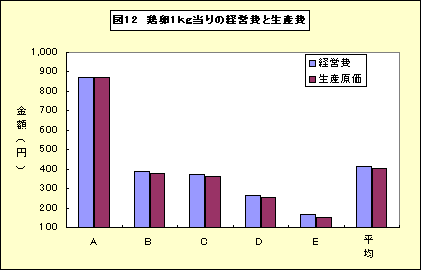
�@�ٗp��͎��{�H�������Ȃ����ƘJ�͂ŏ��낤�Ƃ���o�c�ł͓��R�Ȃ��班�Ȃ����A�ٗp��̕��ς�20.8�~/kg�ł������B
�@�{���̎��Ɣ̔��̃E�G�C�g�������ɂ�A���A��`��A��z���A�̔��萔���̂�����̔���������Ă���B�Ώ۔_�Ƃ̕��ς�13.74�~�ł��������A���̂������ɂ��Ȃ�o��������Ă������������B
�@��������z�ɂ�闧�h�ȕ�����K�v�ł��邪�A�ŋ߂̓S�~���o���Ȃ��悤�ɁA���A���̐ߖ���l���A�i����ێ����Ĉ��S�ɉ^���ł�������̕���������̉ۑ�ł���B
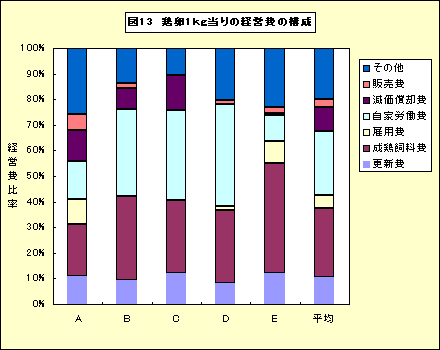
3�D�f�f�_��ʌo�c�����Ɖ��
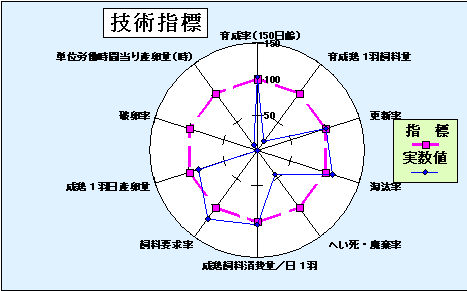 |
�`�{�{��
�Z�p�w�W
�o�c�w�W
���v�� |
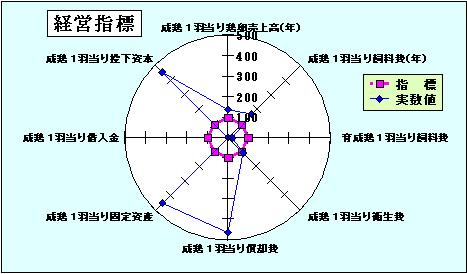 | |
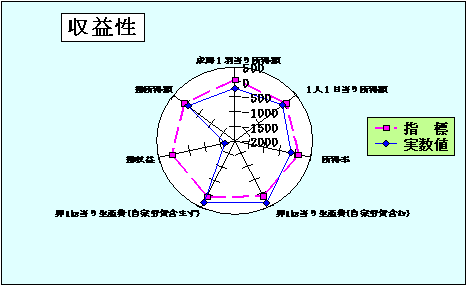 |
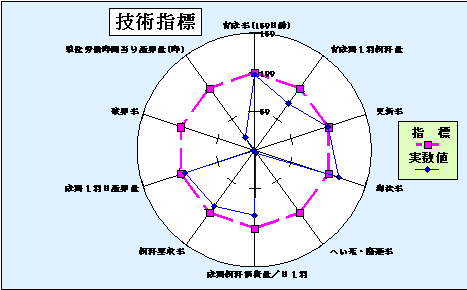 |
�a�{�{��
�Z�p�w�W
�o�c�w�W
���v�� |
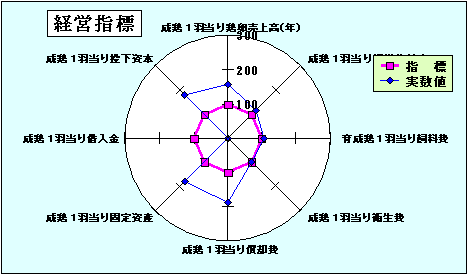 | |
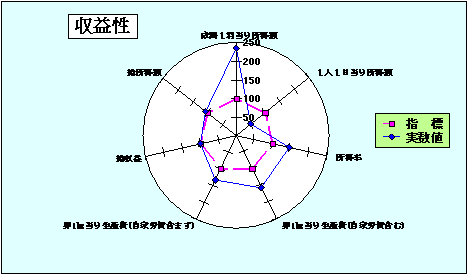 |
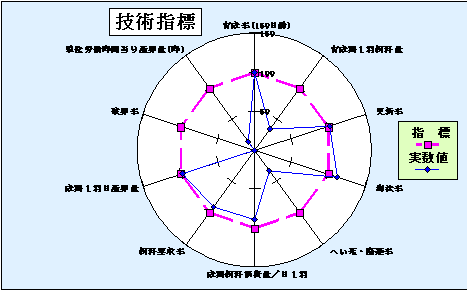 |
�b�{�{��
�Z�p�w�W
�o�c�w�W
���v�� |
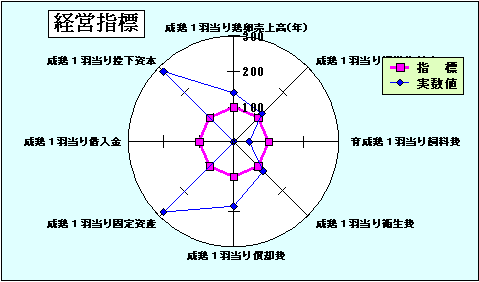 | |
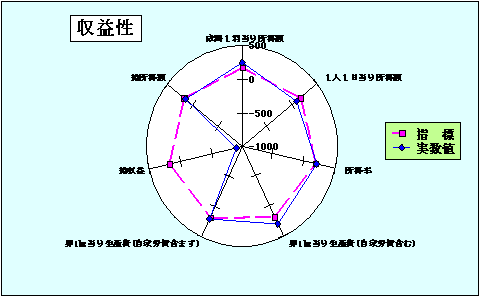 |
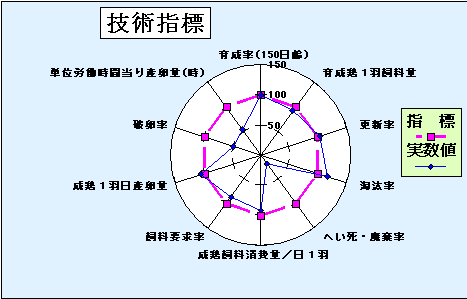 |
�c�{�{��
�Z�p�w�W
�o�c�w�W
���v�� |
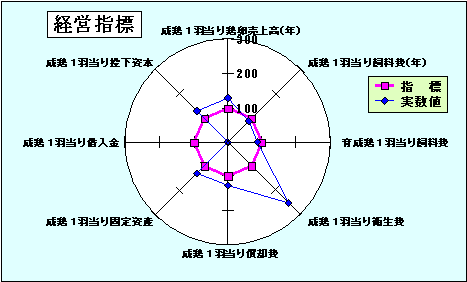 | |
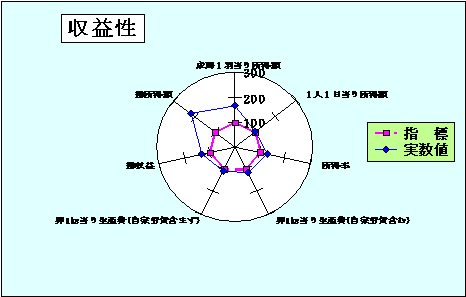 |
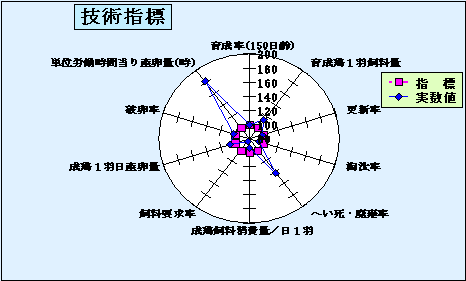 |
�d�{�{��
�Z�p�w�W
�o�c�w�W
���v�� |
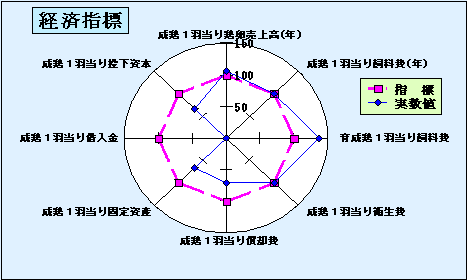 | |
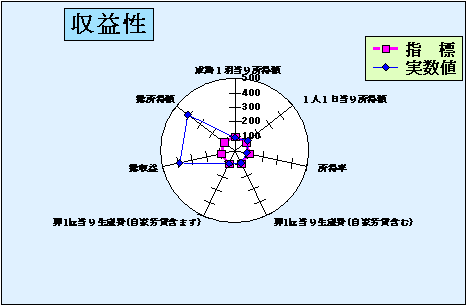 |
4�D�w���̕����Ƒ�
�@����17�N�͉��₩�Ȑ����ŔN�����������A�t�ɂ͈�錧�Ŏ�Ő��ł͂��邪�A���a�������C���t���G���U���������A600���H�̗̍��{����������A�I���錾�͕���18�N�ɂȂ��Ă���ƁA�����ɂ킽��A�{�{�ƊE�ɑ傫�ȉe����^����N�ł������B�@���̂悤�ȏ̒��ŁA�����\���N�Ɏ��{�����f�f�Ώیo�c�ɂ��ĉۑ�Ƃ��̉��P���������ɗ�L�����B
�i1�j�{���̕i���ƈ��S���̊m�ۂ͍ŏd�v�ł�
�@�{���̈��S���̊m�ۂ͌{�����Y�̔��ɂƂ��čł��d�v�Ȏ����ł���B���C���t���G���U�̔����ȍ~�A����҂̈��S�ɑ���ڂ͌������Ȃ��Ă���B�H�i�q����̖�蔭���́A�{���̏���ɒv���I�ȑŌ��ƂȂ�B�o�c�҂͌{���̕i���ƈ��S���ɂ��ď�ɓw�͂��A����u������ŏ���҂��[�����A�ڋq�̊m�ۂɓw�߂邱�Ƃ��d�v�ł���B�@�����̃o�����X����邽�߁A���{�Ǘ��ŎY�������������邱�Ƃ����X����B�������A�{�ɂ͂��Ȃ�̃X�g���X�ƂȂ�A�Ɖu�@�\�̒ቺ���爫�ʋۂ̑��B�����i����邱�Ƃ�����B�����ɘa����Y���������������Ă���B�V�����Z�p�̎�������d�v�ł���B
�i2�j����҃j�[�Y�ւ̓K�ȑΉ�
�@����҂͑��l���ł��邽�ߗ{�{��Ƃ��Ă͕t�����l���A���ꗑ���ɑ��Đ₦���V������g�݂��K�v�ł���B�@�܂��A�{���̕\�����ł͌�������ψ�������ǂ���{���̕\���̓K�����ɑ���v�]�����Y�Ғc�̂ɏo�Ă���A�K���\�����d�v�ƂȂ��Ă���B���ɁA�t�����l���ɂ��Ă͌��������K��{�s�K���̒�߂ɋ��邱�ƂɂȂ�B���̓_���̗{�{��͏���҂ƒ��ɐڂ��邽�ߏ��i�i�{���j�̕t�����l�y�ѓ��ꐫ�ɂ��āA�[���̂������������邱�Ƃ��o����̂ŗL���Ȕ̔��Ƃ�����B
�i3�j���Y�R�X�g���ӎ�����
�@�L���̔���W�J���Ă���o�c�ł́A�Ƃ�����ΐ��Y���Ƃ��R�X�g�ɑ���ӎ���S���ɂȂ�X��������B�������A�{�̈����ǂ͏�ɐi�߂��Ă���A�\�͂ɂ��������{�Ǘ������Y������ƃR�X�g�ጸ�ւȂ���d�v�ȍ��ڂŁA�{�{�o�c�ɉ����Ă͏�ɒ��ӂ��Ă����K�v������B�@�����ێ�ʂ͌o�c�ɂ���Ă��Ȃ�̊J�������邱�Ƃ���A���a�@���l���Ď��{�Ǘ����s�����Ƃ��d�v�ł���B������100%�߂��A���ɗ����Ă���A��X�̗v�����獡�㌴�����i�̏㏸�͔������Ȃ��ƍl������B
�i4�j�{���̐��Y�ʂƔ̔��ʂ̒����ɂ�閳�ʂ̂Ȃ��o�c
�@�S�ʂ̂��Ă���o�c�ł́A�����ɂ���Ď����ɃA���o�����X��������B�{�̃��[�e�[�V���������ɍs���Ď����̃o�����X�����킹��͎̂���̋ƂƂ�����B���̂��߁A�]�藑�̔�����̔����̕s���ɋꗶ���Ă���P�[�X��������B�������牵�≮��f�o�Z���^�[�Ƃ̎���̎��т�����āA�M���W�ɂ��邱�Ƃ���̕���ł���B�@�܂��A�p�\�R�����̕\�v�Z��p���āA���̓��������i�����A�H���j�ƎY������̎�@��p�������{�̃��[�e�[�V������_��̎���ɍ��킹�ăV�~�����[�V��������̂��o�c���l����ꏕ�Ȃ�B
�@�]�藑�A�j���A���ʗ��ʂȂ����H�i�����j�̔����A�o�c����ɓw�߂Ă���{�{�������A�̔��̍H�v�͏d�v�ł���ƍl������B
�i5�j�{�Y�����ɂ���
�@�{�Y��3�@������16�N11�����{�s����A�{�Y���ɑ����ʂ̖ڂ͌������Ȃ��Ă���ƍl������B��ʓI�ɓs�s���ł̒{�Y�o�c�ł́A�n��Z���̐����ɉe�����y�ڂ����L�A�����A�n�G���̔����h�~�ɂ��āA���Ȃ萮���E���P����Ă������A�X�Ȃ�z�����d�v�ł���B�@�܂��A�����̗{�{�ꂪ�_�ݓI���z�ɂȂ������ƂƁA���N�`���̊J���E���y���ɂ���Č{�a�̔����͌������Ă���B�������A�ߔN�͗A�������ɂ��{�a�Z������w�뜜����B��U�`���a����������Ɛr��Ȕ�Q�ƂȂ�̂ŁA�{�a�̗\�h�ɂ͖��S�������đՂ������B