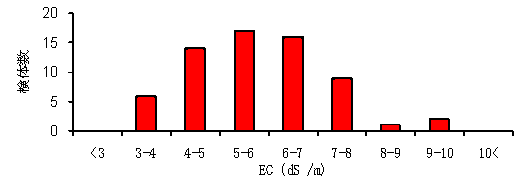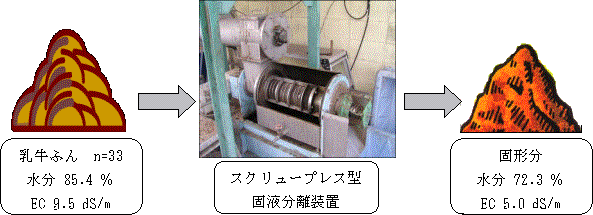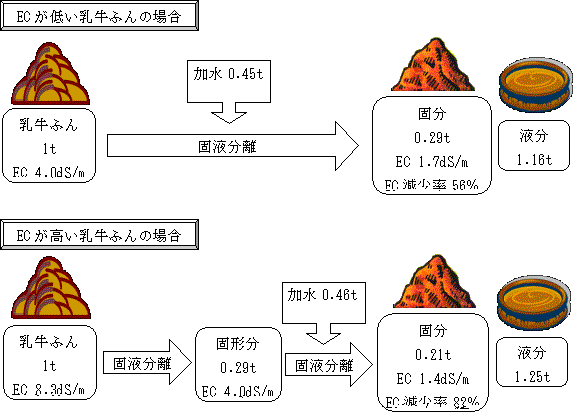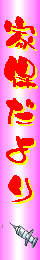このページはIE5.5以上でご覧ください。画面解像度1024×768ピクセルで最適化しています。
平成23年3月号(第603号)

子どもたちが乳牛とのふれあいを通じて命の尊さや食の大切さを学ぶ、「わくわくモーモースクール」を県酪農教育ファーム推進委員会(事務局 県酪農業協同組合連合会)が主催で、平成二十三年二月八日(火)、川崎市高津区の市立末長小学校にて開催した。
県内の酪農家八名と親牛二頭、子牛二頭とともに訪れ、校庭では、酪農家が日本大学の生物資源科学部の方々の協力を得ながら、乳搾りや子牛のブラシがけ体験のほか、「餌の話」「道具の紹介」「牛の一生」「牧場の仕事について」など生乳生産に関する話を行った。
また、教室や体育館では乳業メーカー(明治乳業・森永乳業・雪印メグミルク・タカナシ乳業)の協力を得て、「工場で牛乳が製造され、学校に届くまでの過程」のVTRの放映や「生乳からどの様な食品(バター・チーズ・ヨーグルトなど)が作られているか」の話を行い、製品なども展示した。バター作り体験では、実際に自分達で作ったバターをクラッカーに塗り試食をしてもらった。
この他、県農政部畜産課・県農業技術センター畜産技術所・県大野山乳牛育成牧場の方々により、牛の体の構造についての授業を行った。
このわくわくモーモースクールに児童九百四十四名と父兄らが参加したが、実際に搾乳体験や子牛に触れた子どもたちは、「おおきい」「かわいい」「あったかい」などと言いながら、命を感じとっているようだった。
父兄らは「貴重な体験ができた」「命の循環というものがわかった」

「酪農家さんの苦労がわかった」「牛乳は優れた栄養食品だ」「牛乳をたくさん飲むようにします」など
話していた。
一方、学校側では、「普段ではみられない子ども達の生き生きとした姿が見られた」「総合的な学習ができました」など開催して本当に良かったと話していた。
今回で三回目の開催となるが、普段学校給食で飲んでいる牛乳がどのような過程で作られるか知ってもらうことと国産牛乳の安全性を知ってもらうこと、また県内酪農家の必要性や牛乳乳製品への理解を深めてもらうことも狙いで開催している。
今回は、韓国の口蹄疫発生による防疫の関係で、先生方の出勤前の早朝から学校に出向いて消毒、ふれあい前後の消毒等、防疫体制に気を配っての開催となった。
今後も状況が整えば、年一回「わくわくモーモースクール」を開催して行きたいと思います。
(県酪連 総務部)

神奈川一酪農業協同組合では、平成二十三年一月二十一日に臨時総会を開催し、定款及び定款附属書役員選任規程の一部変更(組合名称、役員推薦委員選出区域)が決議され、神奈川県知事より平成二十三年一月三十一日付けで認可されました。
今回の名称変更は、県内酪農団体の組織整備が進められる中、県内組織の一本化を目指す酪農組合の生産者三十七名が昨年十一月一日に正組合員として新たに加入された事に伴い、組合の一層の発展を期す転機として組合名称を『かながわ酪農業協同組合』に変更されました。
今後とも、『神奈川一酪農協』同様『かながわ酪農協』に相変わらずのご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(かながわ酪農協)

平成二十三年二月二十八日、かながわ和牛受精卵移植協議会主催で、神奈川県、県家畜商業協同組合その他関係団体の協力のもと、県家畜集合センターにおいて「第一回かながわ産黒毛和種子牛品評会」が盛況に開催されました。

品評会には、平成二十一年度から始まった県の補助事業「かながわ産牛肉地産地消推進事業」により生産された子牛の他、県内で生産された黒毛和種の子牛十一頭が集まり審査が行われました。
《審査結果》
最優秀賞:安藤幸宏氏(厚木市)
ふくやす号
(安福勝―糸福―平重勝)
優秀賞:沼上勇氏(茅ヶ崎市)
かつただふく号
(勝忠平―福之国―福桜)
優良賞:田中浩典氏(伊勢原市)
安福勝号
(安福久―平茂勝―紋次郎)
相原孝行(中井町)
くにただつる号
(勝忠鶴―北国7の8―紋次郎)
審査講評、褒章授与の後に出品子牛は全頭家畜市場に上場し、県内肥育農家に高値でセリ落されました。
今後も、子牛品評会を開催することで、受精卵移植技術を活用して和牛子牛を生産する酪農家と県内肥育農家との意見交換を図り、更なる酪農家の哺育技術の向上を目指すことが望まれます。
近い将来「かながわ産牛肉地産地消推進事業」の目的である県民に安全で安心な「かながわ産牛肉」を供給するため、県内の酪農家と肥育農家の連携により生産された和牛の新たな生産体制の構築による畜産経営の持続的発展に繋がることが期待されます。
(経営指導部 倉迫)


低迷する個人消費の状況を打破し、県内産鶏卵の消費拡大を推進するため、養鶏部会、トリ研究会、畜産会の三団体で、二月四日から五日に、平塚市のJA全農神奈川県本部事業所で開催の農業機械展総合展示会場でPRを行いました。
たまごプリン、カステラ、玉子かけ醤油等卵加工品の販売や、ほかほかの鳥シュウマイや焼き鳥の販売、一回五〇円のチャリティーとして色分けしたゴルフボールの掴み取りによる卵のプレゼント、
また、県内鶏卵直販売所の一覧表やたまご知識の冊子の配布等を行いました。
イベントを通して県内の鶏卵生産者の存在や経営状況を県民に知って頂くとともに、卵価値上げへの理解醸成にも繋がって行くことを期待しています。
(経営指導部 岸井)


高病原性鳥インフルエンザについては、昨年十一月に島根県、その後、宮崎県、鹿児島県、愛知県、大分県、和歌山県及び三重県で発生が報告され大流行となっています。更に全国各地で死亡野鳥や水鳥等からウイルスが検出されるなど、本県での発生リスクも高まっていると考えられます。
このため、養鶏農場における本病の侵入防止の一助とするため、神奈
川県の後援をいただき、次のとおり講習会を開催します。
日時:平成二十三年三月十五日
(火)・十三時三〇分から
場所:メルパルク横浜
横浜市中区山下町一六
℡045―661―8155
講演内容
①高病原性鳥インフルエンザについて(仮題)
迫田義博氏(北海道大学大学院微生物学教室准教授)
②神奈川県内の畜舎に飛来する野鳥について(仮題)
加藤千晴氏(自然環境保全センター 副技幹)
③高病原性鳥インフルエンザの防疫について(仮題)
~発生時の移動制限区域内の早期鶏卵出荷のために~
甲斐 崇氏(県央家畜保健衛生所 主査)
(家畜衛生部 萩原)




今後起こりうる諸外国産畜産物との販売競争に対抗できる国産畜産物の生産・販売のあり方を見出すため、県畜産課、県畜産技術所、全農神奈川県本部、県養豚協会、県畜産技術協会との共催により、情報発表会及び講演会を次のとおり開催します。
日時:平成二十三年三月十八日
(金)・午前十時から
場所:海老名プライムタワー
海老名市中央二―九―五〇
℡046―235―2010
内容
《現地情報・研究情報発表会》
十時~十一時三〇分
①豚のアニマルウェルフェアの取組み
(西田浩司 主任研究員)
②系統豚の現状と利用
(山本 禎 主任研究員)
③消費者調査から見た求められる豚肉の特徴
(引地宏二 主任研究員)
④データから見た肉豚改良の現状
(阪本雅紀 副技幹)
《養豚関係団体講演会》
十二時三〇分~十六時
①最近の国際化の動きと今後の国内畜産業への影響
鈴木宣弘氏(東京大学大学院農学研究科教授)
②食品リサイクルループは命をつなぐ環~ユニー(株)のエコフィード利用への取組み~
百瀬則子氏(ユニー(株)業務本部環境社会貢献部)
(経営指導部 橋本)

二月二十二日・ニュージーランドのクライストチャーチ付近で大地震があり、多数の死傷者が出ました。十六年前の一月の阪神淡路大震災、その後は中国で、スマトラ沖で、一年前の一月にはハイチ共和国のポルトープランスと地震続きです。ニュージーランドではライフラインが切断されて、被災者の方々はポリタンクを持ち寄って水をもらっていました。テレビ画像の彼等は整然と並び「皆に行き渡るようにね」と言っているのがとても印象的でした。一年前のポルトープランスでの支援物資の奪い合いや商店から略奪する画像を思い出し、その違いに感心しました。十六年前の阪神淡路の時の外国のメディア関係者が「日本では奪い合いや略奪が無い」と感心していたのを思い出しました。物資が豊富なればこそのことでしょうか。
太平洋戦争の終戦時、戦闘車両のジープに乗って来た米兵が群がる日本の子供たちにチョコレートを投げて、それを我先に拾ったことを思い出しました。丁度自分の方に飛んで来たチョコレートをポケットに入れて意気揚々と家に帰えったところ、軍隊帰りの兄に「恥を知れ!」と、こっぴどく叱られたことを憶えています。でも、あのチョコレートは旨かったなー、生まれて初めての美味しいたべものでしたね。「衣食足りて礼節を知る」のでしょうか。「武士は食はねど高楊枝」とはいきませんなー。
その後学校給食が始まり、初めて喰った肉は南氷洋のビーフステーキ?=鯨肉でした。鯨の竜田揚は上等品、噛んでも噛んでも噛み切れないチュウインガムみたいなベーコンでも給食は嬉しかったなー。先日泊まった宿の朝食で飲んだ牛乳は昔の給食を思い出させてくれました。「これは何?この味は?」『ええ、天然の牛乳ではありませんから』ときたもんだ。昔の米国の放出品の脱脂粉乳は不味くて飲めない子もいましたね。
今も救出作業が続くクライストチャーチでは一〇〇人近い方々が亡くなり、三〇〇人にも及ぶ安否が不明。亡くなられた方々の最後の朝食
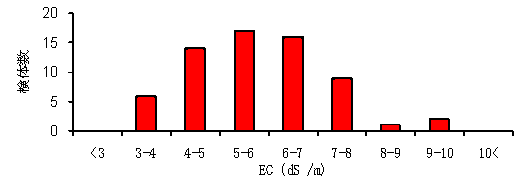
図1 神奈川県内酪農家における堆肥化材料の電気伝導率(EC)の分布
|

写真1 当所フリーストール牛舎でのスクレイパーによる除ふんの様子
|
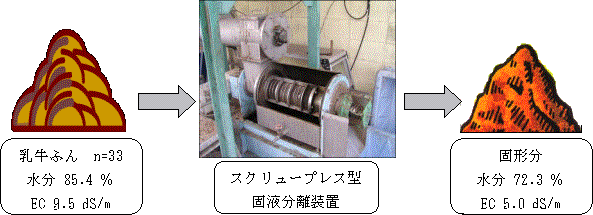
図2 スクリュープレス型固液分離装置で乳牛ふんを固液分離した時の水分とECの変化
|
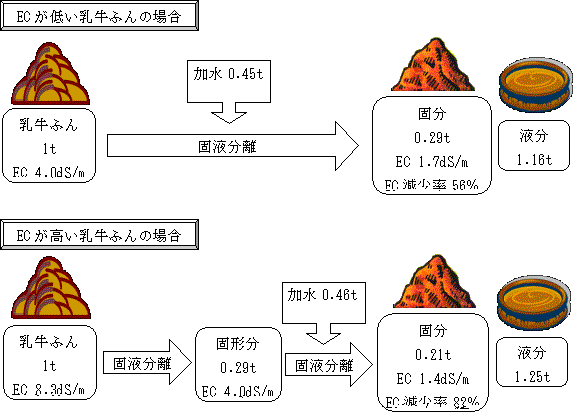
図3 スクリュープレス型固液分離装置による塩類の除去方法
|
表1 固形分の堆肥と乳牛ふん堆肥の肥料成分組成
|
pH |
EC
(dS/m) |
TC |
TN |
C/N |
P2O5 |
K2O |
CaO |
MgO |
| (DM%) |
(DM%) |
低
塩
類
堆
肥 |
Lot.1 |
8.2 |
1.7 |
45.6 |
1.5 |
31.0 |
0.9 |
0.8 |
0.9 |
0.6 |
| Lot.2 |
7.4 |
1.1 |
44.4 |
2.5 |
17.9 |
0.5 |
1.3 |
1.7 |
0.7 |
| Lot.3 |
7.7 |
1.2 |
45.7 |
1.4 |
33.4 |
0.9 |
0.9 |
0.4 |
0.1 |
| Lot.4 |
8.0 |
0.9 |
42.8 |
1.5 |
29.4 |
1.1 |
1.0 |
0.6 |
0.4 |
| Lot.5 |
7.6 |
1.7 |
42.3 |
1.9 |
22.6 |
1.2 |
1.0 |
0.9 |
0.5 |
| 乳牛ふん堆肥※ |
8.7 |
4.1 |
40.9 |
2.5 |
16.6 |
2.2 |
2.9 |
1.0 |
1.1 |
| ※:当所発酵乾燥ハウスで製造した乳牛ふん堆肥 |
|
では美味しい牛乳を飲んだだろうか。鯨肉ならぬ羊肉か牛肉を美味しく食べただろうか。そんな事を思いめぐらすと、今宵もほろ苦い酒を飲まずにいられようか。酒食足りて礼節を知る。
(忠九朗)

★はじめに
牛ふん堆肥は豚ふん堆肥や鶏ふん堆肥に比べて塩類濃度が低い傾向にあります。牛ふん堆肥の中でも、塩類濃度の低い堆肥は土壌改良資材として土づくりの目的で利用されています。
近年、家畜ふん堆肥の塩類濃度が上昇していることを平成二十一年十一月の第587号で報告しました。また、土壌に雨が直接あたらない施設栽培や化学肥料を過剰に施肥した畑地の一部では土壌の塩類濃度が上昇していることが報告されています。このような土壌では、塩類濃度の高い堆肥を施用すると植物に生育障害などが起きやすくなります。このような理由から、家畜ふん
堆肥は一部の耕種農家から敬遠されているのです。
そこで、家畜ふん堆肥の塩類濃度を下げれば耕種農家での利用が増えることが期待できます。今回は、塩類濃度の指標として電気伝導率(EC)を示しながら、塩類濃度の低い乳牛ふん堆肥を製造する方法について紹介します。
★堆肥化材料のEC
当然ですが、塩類濃度の低い堆肥を作るには、ふんや副資材など堆肥化材料のECが低いほうが有利です。そこで、県内酪農家38戸から得た堆肥化材料65検体のEC(風乾材料、水10倍添加)を測定してみました(図1)。
堆肥化材料のECは3~9mS/mと幅広い分布を示し、平均は5・8dS/mでした。ECが4dS/m未満の検体は全体の9%、5dS/m未満の検体は22%でした。この調査から、堆肥化材料のECは農家によりかなり差があることがわかりました。では、この差は何が原因なのでしょうか。
★ふん尿分離による塩類の低減
排せつ物のうち、尿はふんに比べてかなり高いECを示します。当所の搾乳牛において、排出直後のふんと尿のECを測定しました。ふんのECは2・6±0・8dS/m(n=27)でしたが、尿のECは60±
13 dS/m(n=26)で20倍以上の高い値でした。この結果から、堆肥化材料のECの差は畜舎でのふん尿分離の程度の違いが原因と考えられます。塩類濃度の低い堆肥を作るためには、畜舎でのふん尿分離を徹底し、ふんに尿が混入しないようにしましょう。ちなみに、当所のフリーストール牛舎はスクレイパーにより除ふんを行っていますが(写真1)、ふん尿分離の程度は悪く、牛舎から搬出されるふんのECは平均8・6dS/m(n=71)と高い値です。
★固液分離装置による塩類の低減
一部の酪農家では、ふんを固形分と液分に分離する固液分離装置を利用してふん処理を行っています。ふんを固液分離すると水溶性である塩類は液分に多く移行すると考えられます。そこで、当所のスクリュープレス型固液分離装置で、フリーストール牛舎のふんを固液分離してみました(図2)。その結果、EC9・5dS/mのふんがEC5・0dS/mの固形分となり、EC除去率は45%でした。固液分離によりECを低減できることがわかりました。
一般に、塩類濃度が低いと言われているバーク堆肥のECは1~3dS/mです。そこで、当所のスクリュープレス型固液分離装置を使って、
EC2dS/m以下の塩類濃度の低い乳牛ふん堆肥の製造方法を検討しました。
乳牛ふんの塩類濃度が低い場合は、加水して固液分離を1回行います(図3)。EC4・0dS/mの乳牛ふん1tに水を0・45t加えて固液分離するとEC1・7dS/mの固形分が0・29tでき、1・16tの搾汁液が発生しました。
一方、乳牛ふんのECが高い場合、1回の固液分離で塩類濃度を低くするためにはふんの3~4倍量の水を加えなければなりません。しかし、これでは大量の水が必要となり、膨大な量の搾汁液も発生します。そこで、手間はかかりますが、1回固液分離した固形分に加水して再度固液分離を行います。EC8・3dS/mの乳牛ふん1tを固液分離し、さらに固形分に水を0・46t加えて再度固液分離するとEC1・4dS/mの固形分が0・21tできました。また、搾汁液の量は1・25tとなり、塩類濃度が低い乳牛ふんを固液分離した場合と同程度の量となりました。
★固形分の堆肥化
固液分離した固形分は、副資材を使用せずにそのまま堆積するだけで60℃を超える良好な堆肥化発酵が生じました(図4)。
表1に固形分を堆肥化して出来た
堆肥の肥料成分を示します。堆肥のECは2dS/m以下となり、カリウム含有率も1%程度で乳牛ふん堆肥の1/3程度となりました。目標の塩類濃度の低い堆肥を製造することができました。この塩類濃度の低い堆肥の特性については、現在、農業技術センターと共同で研究を進めています。
★おわりに
家畜ふん堆肥を耕種農家に広く利用してもらうには、皆さんの作っている堆肥の成分や特徴を把握して、耕種農家にしっかり伝えていくことが重要です。
従来から、塩類濃度の低い家畜ふん堆肥は、土壌改良資材として土壌環境を改善し土を豊かにする、土づくりの目的で利用されてきました。畜産技術所では、この塩類濃度の低い堆肥を野積みや雨ざらしによらない方法で作る技術を研究しています。
皆さんも一度自分で作られている堆肥のECを測ってみてはいかがでしょうか。測定してみたい方は企画経営担当または普及指導担当までご連絡ください。
(神奈川県農業技術センター
畜産技術所 企画経営担当
田邊 眞)
この記事の詳細は、神奈川県畜産技術センターHP
研究情報&技術情報


「県央家保」に
お出かけ下さい | 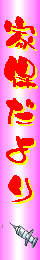 |
家畜保健衛生所は「家保」と略称で呼ばれますが、昨年の宮崎県で発生した口蹄疫やこの冬各地で発生している高病原性鳥インフルエンザの防疫活動などで白い防疫服に身を包んだ職員の姿を報道でも目にすることが多くなりました。しかし、その報道の中でも「家畜保健所」「家畜衛生保健所」「家畜保険衛生所」と抜け落ちたり、ひっくりかえったり、「保険屋さん?」になることもしばしばです。
神奈川県の家保は、平成二十一年度に県央と湘南の二家保に再編整備し、二年が経過しようとしています。県央家保では、この組織再編を
契機に「かながわの畜産」や「家保業務」について、消費者の理解を深めるため「施設公開」や「視察受入れ」などに積極的に取り組んでいます。
今年度の「施設公開」では、口蹄疫について、正しい知識の説明や県内発生を想定した移動制限区域等の防疫措置を体験してもらい、消費者の理解醸成を図りました。
生産者の方々も小中学生等を農場体験学習などで受け入れ、情操教育や食育などに取り組まれていますが、家保でも同様に地元中学校の校外学習である生徒の職業調べを受け入れ、獣医師の仕事について学習の場を提供しています。
また、獣医系大学の学生を実習生として長年受け入れしており、産業動物獣医師が不足している中、多くの実習生が卒業後、全国の生産現場や家保で活躍しています。
この様な取り組みで県央家保への視察者は、再編後二年間で一二〇三名にも昇り、市町村畜産会や獣医師会支部研修会の視察先としても活用いただきました。
生産者の皆さんをはじめ、様々な本紙読者の方々も家保の知らない一面を発見できるかもしれません。お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。
(県央家畜保健衛生所 和泉屋)


この冬は雪が少ないので大助かり、と内心ほっとしていましたが、雪は確実にやってきました。当日は関東一円に大雪注意報が出て、都心部でもかなりの積雪量とのこと。その間は連休三日間に当たり、出番の職員は泊まり込みで、朝には道路の除雪が速やかにできる体制で臨みましたが、予想ほどの積雪はありませんでした。
ところが、その数日後、またもや今度は午後四時ごろから雪が降り始め、みるみる怖いほどの早さで降り積もります。一晩で二〇cmほどの積雪量がありました。翌朝の職員の通勤では、泊りの職員がすっかり除雪を済ませていたので、安全に走行できました。降雪の心配はまだ三月までは続きます。
昨年九月の台風では、放牧地など四十一カ所もの被害を受け、自家施工できるところは応急処置をほぼ終わらせました。自家施工不可能な場所のうち、大野山頂上部分の崩壊箇所(大野山フェスティバルメイン会場)と「まきば館」の横のハイキン
グ道の崩壊部分の復旧工事が二月から三月にかけ、専門業者によって施工されています。雪が降るなど厳しい気象条件下ではありますが、今年度中には完了します。
さて、牧場内の古くなった掲示板や案内図を作り直しました。デザインからすべてが職員の手作りです。当牧場のふれあい施設としての機能も考え、お客様に親しみある絵柄を心がけて製作しました。事務所入り口の案内図には、放牧地に牛のイラストをちりばめ、遠く富士山を配置し、鳥が遊び、事務所には県旗がはためく楽しいものです。ペンキの配合で放牧地の絶妙な草の色など描き出し、色彩豊かな図版になっています。牛舎入り口の案内図には、牧場の仕事をイラストで説明しています。ご来場の折には、ぜひ職員の力作をご覧ください。
(大野山乳牛育成牧場長 青木)