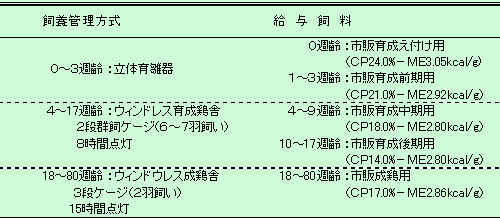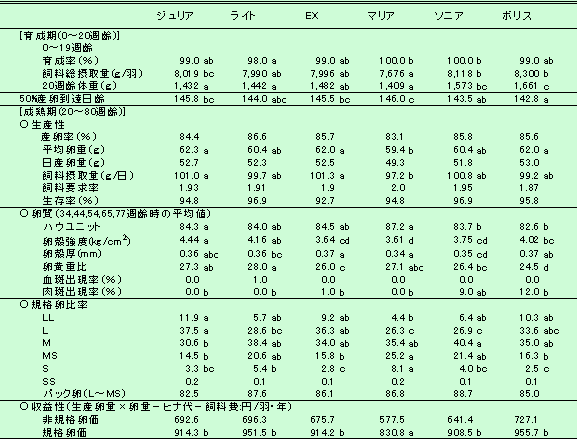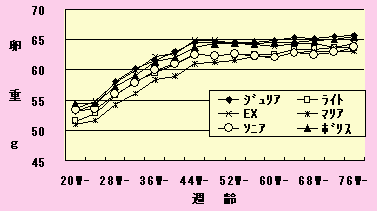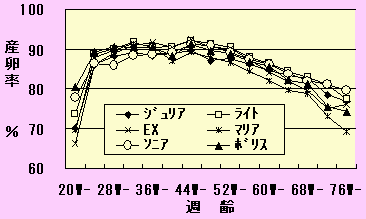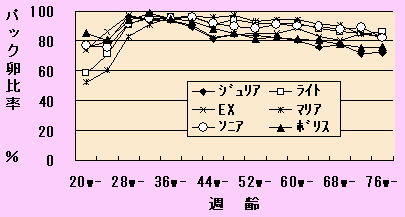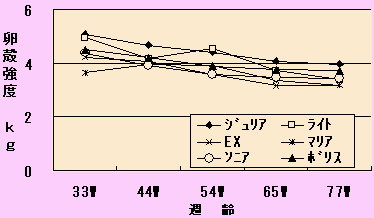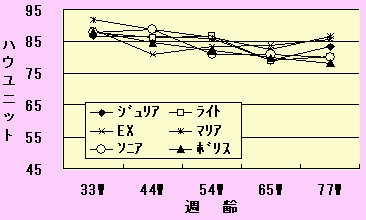このページはIE5.5以上でご覧ください。画面解像度1024×768ピクセルで最適化しています。
平成21年2月号(第577号)

| |
|---|
平成二十年度神奈川県家畜保健
衛生業績発表会が開催される |
|---|

平成二十年度神奈川県家畜保健衛生業績発表会を平成二十一年一月八日伊勢原市民文化会館小ホールにおいて開催しました。この発表会は、家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定所が日常業務で得た業績を広く発表し、討議することによって今後の事業推進の一助とする目的で開催するもので、今年で五十回を数えます。
また、審査時間等には県畜産技術協会開催の畜産セミナーや生活衛生課による特別公演が併せて開催されました。
今回は、酪農・肉牛関係四題、養豚関係五題、養鶏関係三題、その他一題の合計十三題が発表されました。
また、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所の播谷上席研究員、畜産技術センター所長、家畜病性鑑定所長、畜産課長代理により、助言と審査が行われ、関東甲信越ブロック家畜保健衛生業績発表会(●)への参加課題が選出されるとともに、日本産業動物獣医学会関東地区大会(●)、関東甲信越地区鶏病技術検討会(●)、神奈川県獣医師会症例発表会(●)への参加課題が推薦されました。
なお、今回の概要は次のとおりです。
・横浜農協酪農部会のバルク乳細菌検査による搾乳衛生指導
田中嘉州(東部家保)
・「問いかけ」~酪農家自身が目標を認識し、より主体的に取り組み始
めるためのサポート~(●)
島村 剛(湘南家保)
従来、我々は農場の生産性向上を図るため家保から農家へ主に一方的な技術指導を行ってきた。しかし、それだけでは改善されない農場も少なからず存在する。そこで今回、白血病対策の中でも具体的に改善されることの少ない初乳対策を例に「問いかけ」を主体とした双方向的な手法で改善を図ったので報告する。
問いかけは「白血病とは何か」「原因」「困ること」「今後の目標」等農場に答えを求めながら進め、最後に「目標達成に向けた経営に合った対策」を問いかけ、考えてもらった。また問答中、不足と感じる点があれば獣医学的知見を持って補足した。その後、複数の農場で経営に合った初乳対策を開始。加温器を自作した農場もあり、この農場では実施前三六%であった育成牛白血病抗体陽性率が〇%となり、全頭預託検査に合格するようになった。
問いかけは課題から解決法まで農場自身に考え決定してもらう双方向的手法である。これは参加型手法と呼ばれる手法理念に基づき実施しており、考え方は「指導」より「支援(サポート)」が相応しく、すべての決定を農場自らがすることで主体的意欲向上が図られる。
生産性向上を図るには農場の主体的意欲向上が必須。今後、我々は従来の指導法に加え、参加型手法を始め様々な手法を取り入れ、農場を支援していくことが、個々の経営向上、ひいては更なる畜産振興につながるものと考える。
・管内における豚オーエスキー病(AD)清浄化
森村裕之(湘南家保)
・〝出来ること〟から始める豚慢性疾病対策
河本亮一(県央家保)
・小規模養鶏に対する家畜保健衛生所のアプローチ
広田一郎(湘南家保)
・足柄家保における高病原性鳥インフルエンザの防疫体制(●)
宮下泰人(足柄家保)
高病原性鳥インフルエンザ(以下「HPAI」)は、平成十六年一月に七十九年ぶりに山口県で発生、防疫体制の構築が急務となり、次のと
おり整備した。
平成十六年十二月に神奈川県HPAI発生時対応マニュアルが策定され、地域の畜産関係機関との連携体制について確認した。
平成十七年十月に管内最大の養鶏場での発生を想定した貿易演習を実施、必要な防疫作業とこれにかかる日数、資材、人員といった具体的な準備内容を関係機関とともに確認。この時の問題点は、殺死体の処理方法、地域内防疫体制の確立、近隣他県との防疫体制の確立だった。
殺死体の処理は、管内での埋却は不可能で、焼却処理するため一般廃棄物処理場を調査。三施設のうち二施設について利用可能であることを確認した。
現地対策本部(以下「現地本部」)の体制については、平成十九年二月に足柄上地域、平成二十年六月に西湘地域県政総合センター(以下「センター」)安全防災課と協力し、構成機関の連絡体制、役割分担、連携体制について確認した。
静岡県東部家畜保健衛生所と平成十九年二月に県境防疫会議を開催、HPAIが発生した場合の連絡体制と防疫活動に必要な情報を交換した。
平成二十年四月にオオハクチョウからHPAIウイルスが分離されたことで、センター環境部と死亡野鳥対応について連携体制を構築した。
今後は、各市町の実情に即した防疫体制を構築したい。
・データベース「轟君」と「収New君」による業務改善
田中嘉州(東部家保)
・管内における牛ウイルス性下痢ウイルス2型(BVDV2型)の浸潤状況について
松本 哲(湘南家保)
・牛白血病抗体陽性が乳質及び繁殖に及ぼす影響
池田暁史(足柄家保)
・県内初の豚サーコウイルス2型(PCV2)genotype1確認事例(●)
石川 梓(東部家保)
管内二農場(A、B)において、PCV2genotype1の感染が県内で初めて確認されたのでその概要を報告する。
平成二十年二月~五月に上記二農場から発育遅延豚及び死亡頭数増加
の連絡があり、発育遅延豚五頭の病性鑑定を実施した。結果、全症例について豚サーコウイルス関連疾病(PCVAD)と診断した。さらに、平成十八年からの死亡頭数を調査した結果、二農場とも事故率の上昇が認められ、農場内でPCVADが流行していると判断した。
そこで、今回の事故率上昇とPCV2の遺伝子型との関係を調査するため、二農場の過去保存血清及び病性鑑定豚の臓器乳剤等を用い、PCV2の浸潤の有無及び遺伝子型の調査を行った。結果、A農場では平成十八年六月の検体からgenotype2が検出されたが、平成二十年二月及び五月の検体からはgenotype1が検出された。また、B農場では平成十八年七月の検体からgenotype2が検出されたが、平成二十年五月の検体からはgenotype1が検出された。
二農場とも事故率上昇前にはgenotype2が検出されていたが、事故率上昇後にgenotype1が検出されており、genotype1が事故率上昇の一因であると推察された。
・過去9年間の病勢鑑定成績からみた豚の複合感染症の推移(●)
松尾綾子(病 鑑)
近年、全国的に豚サーコウイルス2型(PCV2)や豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス(PRRSV) などの様々な病原体が関与した発育不良や事故率の上昇が問題となっていることから、本県における過去九年間の病性鑑定豚百十九件二百十八頭からみた豚の複合感染症の推移について検討した。
病性鑑定依頼の主な目的は、哺乳中や離乳後の豚では下痢が、肥育豚では発育不良及び呼吸器症状の原因究明であった。病理組織学的検査では約九〇%に肺炎が認められ、間質性肺炎は六〇%、化膿性肺炎は四十五%であった。細菌学的検査ではパスツレラ、アクチノパチルス、サルモネラ等が分離された。
このうち百四十四頭についてPCR法によりPCV2及びPRRSVの遺伝子検索を実施した結果、哺乳豚はともに全て陰性であったが、十九年以降は八十%が陽性となった。四十一日齢以上肥育豚では陽性率が五〇~八〇%で推移してきたが、十九年以降は全例陽性となり、遺伝子
型判別で一部の農場でgenotype1が検出された。一方、PRRSVは、離乳豚では約三〇%が陽性で、肥育豚では十二~十四年は七〇%、十五~十七年は四〇%、十八~二十年は七〇%が陽性であった。以上のように、本県でも遺伝子検索の結果等からPCV2及びPRRSVの浸潤が進み、他の病原体と複合感染することにより、近年の離乳後の発育不良や事故率の上昇に関与していることが示唆された。
・県内の病勢鑑定豚から分離されたSalmonella Choleraesuisの性状について(●)
小菅千恵子(病 鑑)
Salmonella Choleraesuis(SC)は、豚に宿主特異性が強く急性敗血症等を起こす。本県の病性鑑定では平成九年からこれまでに二十二件二十八頭から分離されている。今年度、増加傾向を認めたため、その性状について比較検討した。年度別分離状況では、九、十年が各四件、その後は〇~二件で推移したが、二十年は四件五頭と増加した。地域別では六市十五戸に分布し、A市が六戸と多く、二十年はA市と隣接するB市の三戸で分離された。日齢別では若齢豚からは分離されず、肥育前期が半数を占め、共通して削そう、チアノーゼ、発咳等を認めた。SCは肺、肝、脾等から分離され、PCR検査ではPCV2特異遺伝子が二十年SC分離豚全頭から検出された。分離菌の生物学的性状は、四十株中三十七株がKunzendorf型で、十二年十、十二月に一戸二頭から分離された三株が硫化水素非産生のcholeraesuis型であった。薬剤感受性検査(一濃度ディスク法)では九五%の株がSM、OTCに体制、四薬剤以上の耐性株は四戸でみられ、農場毎に同様の耐性パターンを示した。プラスミドプロファイルでは二十一株中二十株が五〇kbpを保有し、十六株は五〇kvpのみを、他は別パターンを示した。Xbalで処理したPFGEバターンでは、九、十年のⅠ群、十二年のⅡ群、十四年以降のⅢ群と個別のⅣ~Ⅴ群に分類され、二十年の株はすべてⅢ群であった。以上、近年分離されたSCはほぼ同様の性状を示しており、今年度の増加は、新たなSCの侵入
によるものではなく、PCV2等の他要因の関与によるものと考えられた。
・マイコプラズマ・シノビエ血清平板凝集反応における馬血清混合による非特異反応除去(
●)
池田 知美(県央家保)
マイコプラズマ・シノビ(SM)の血清平板凝集反応(SPA)は、遺伝性ファブリキウス嚢病の不活性ワクチンやニューカッスル病のオイルワクチン接種鶏等では非特異反応が起こることがあるが、被検血清に異種動物の血清を混合すると除去できるとの報告がある。今回、馬血清混合による非特異反応の除去について検討した。最初に、被検血清に対し、①PBS等量、②馬血清五分の一量、③馬血清等量を混合してSPAを実施し、陽性又は疑陽性と判定した割合(以下、凝集率)を比較した。被検血清のみでの凝集率は九一・五%だったが、①は八八・七%、②は七五・二%、③は六四・五%で、凝集率は③で最も低くなった。次に被検血清を日齢でA:百日齢未満、B:百~二百日齢未満、C:二百日齢以上の三グループにわけ、被検血清のみでSPA陰性又は疑陽性と判定された血清のうち馬血清を等量混合すると陰性に転じた割合(以下、非特異反応率)を比較した.Aは六三・六%、Bは三九・四%であったが、Cは〇%で、非特異反応はAが最も高かった.以上の結果、MSのSPAを実施する際には、鶏群のワクチネーションプログラムを把握することだけでなく、MS野外感染の可能性が低い若齢鶏群を検査する場合には、非特異反応を考慮し被検血清に馬血清を等量混合した検査を行うことが必要である。
以上、発表内容に興味がある方、詳しく知りたい方は、家畜保健衛生所、家畜病性鑑定所にお問い合わせ下さい。
(畜産課 平山静雄)

(社)神奈川県畜産振興会(志澤勝会長)では、毎年畜産関係団体と協力し、県内の畜産を理解してもらい、併せて県内畜産物の消費拡大を目的に畜産フェスティバルを開催しているが、昨年畜産技術センターで開催した「家畜に親しむつどい」並びに大野山牧場での「大野山フェスティバル」でそれぞれ豚汁、バーベキューの試食コーナーを設けた。
その際募金箱を用意し、福祉事業に寄付する目的で参加者に百円の寄付をお願いして集めた浄財に、畜産振興会が独自の資金を加えて一月十三日県社会福祉協議会(林秀樹会長)の「かながわ交通遺児支援基金」にと二十万円を寄付した。
経済状況が日増しに厳しくなる中で交通遺児の援護に少しでも役立つことを願っています。
(総務部)

~乳用種・交雑種に生産者補給金が交付されます~
黒毛和種 三八〇、四〇〇
交雑種 一五八、一〇〇
乳用種 八三、七〇〇
乳用種は保証基準価格(一一六、〇〇〇円)・交雑種(一八一、〇〇〇円)をそれぞれ下回りましたので、その差額、乳用種三二、三〇〇円、交雑種二六、九〇〇円の生産者補給金が交付されることになりました。
黒毛和種は保証基準価格、合理化目標価格を共に上回っているので、生産者補給金の交付はありません。
((社)神奈川県肉用子牛価格
安定基金協会)


オバマ氏はチーズバーガ
ーがお好き、日本人は
鮨、鮨は鮪 |
WWF(世界野生生物基金)とグリーンピースの思想に傾倒している日系イタリア人から海洋生態系を乱さないために全種類の鮪を絶対食べないで・・・との手記が送られてきました。
世界の広い範囲で食べられている家畜の肉は日本でも必需品ですが、日本の食卓から鮨(寿司)の上ネタである鮪のすべてを取り除かれては、日本の食文化を否定されたのと同然でしょう。お正月の御節料理と並んで刺身や鮨は日本の食文化の原点であり、そのネタの鮪は必需品です。
絶対に近づいたといわれているクロマグロやミナミマグロには漁獲制限は必要でしょうがメバチ、キハダやビンナガは漁獲方法等を制限しながら正規の市場を通じて食卓に乗せて頂きたいものです。鮪の流通のすべてを停止したら魚河岸で働く鮪専門の職人さん達の、あの素晴らしい熟練技術は宝の持ち腐れになってしまいます。
なぜ、西洋の人達は他の民族の習慣を踏み躙ることに平気なのでしょうか。鯨を食うな、鮪を食うな、更には鮪の立場になって考えろ・・・となると、生きとし生けるものの命を貰って生きている人間の立場、食べられるために生かされている家畜の立場はどうなのでしょうか。グリーンピースの団員は世界会議で認められた調査捕鯨船の航行を妨害して船員に硫酸瓶を投げつけたりしましたが、鯨のためなら人間を傷つけても良心が痛まないのでしょうか。
一月二十日、アメリカ合衆国ではバラク・オバマ氏が新大統領に就任されました。彼の生い立ちはハワイで生まれ育ち、インドネシアでの生活経験もある由。異人種、異民族に寛容な「アロハ・スピリット」を自然と身につけているそうです。彼はチーズバーガーとナッツが大好きだそうですが、ハワイの魚をネタにした鮨はどうか聞いてみたいですね。
麻生さんんにお願いして、大統領を日本にお招きして鮪の鮨をご馳走してみては如何でしょうか。オバマさんは異なる民族の異なる食習慣に寛容な施策を世界に訴えてくれるかもしれません。
「うーん、マグロは旨い!
チーズバーガーからマグロに
チェンジだ!」と
いってくれないかな?
(忠九朗)


現在、国内には多くの種類の採卵鶏の銘柄が流通しており、この中から自分の経営に合った銘柄を選定するのは難しいことと思われます。そこで、本県で普及している採卵鶏の銘柄について、それらの特質と能力を明確にし、養鶏農家のみなさんの銘柄選定の一助とするため、経済検定を毎年実施しています。
この度、平成一九年二月にえ付けした採卵鶏の成績がまとまりましたので、お知らせします。
飼養期間は平成一九年二月から平成二十年九月までの八〇週間です。
供試鶏は白玉鶏のジュリア、ジュリアライト(ライト)、シェーバーEX(EX)、マリア、ピンク玉鶏のソニア及び赤玉鶏のボリスブラウン(ボリス)の六銘柄です。
飼養方法は、表1のとおり、養鶏農家で一般に実施されている方法を用いました。
各銘柄の検定成績は、表2及び図1~5のとおりで、その概要は次のとおりでした。
(一)育成期
育成率は、全銘柄で九八%以上と良好でした。二〇週齢体重は赤玉鶏のボリス、次いでピンク玉鶏のソニア
表1 飼養方法
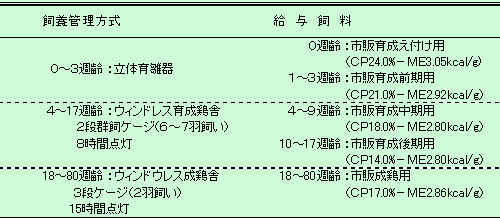 |
表2 平成19年え付け採卵鶏の経済検定の成績(0~80週齢)
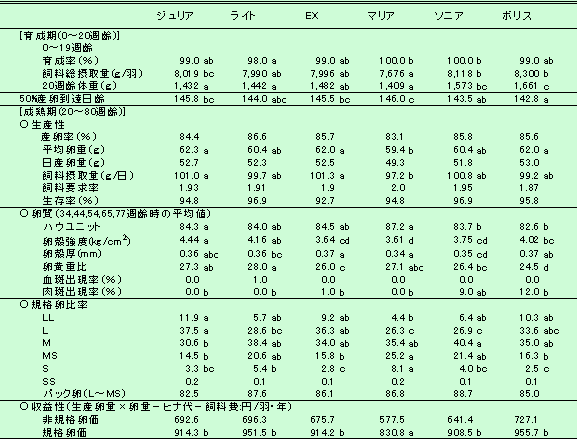 |
が重く、ジュリア、ライト、マリアが軽い傾向でした(統計的有意差あり。以下、P<0.05)。〇~一九週齢の飼料摂取量は、体重が重かったソニア、ボリスが多く、体重の軽かったマリアが少ない値でした(P<0.05)。
(二)成鶏期(生産性)
五〇%産卵到達日齢は、赤玉鶏のボリスが一四三日齢と早く、最も遅かったマリアとの銘柄間の差は三日程度でした(P<0.05)。
産卵率は、全銘柄が八〇%以上と良好でしたが、五二週齢以降マリアが他の五銘柄に比べて、やや低く推移しました(図1)。
平均卵重は、マリアが軽く、ジュリア、EX、ボリスが重く(P<0.05)、
マリアとジュリアの差は約三g程度でした。図2に示した平均卵重の推移ではジュリア、ボリスが、産卵全期にわたって他銘柄に比べて卵重が重く推移し、EXは産卵前期までの卵重増加が早いが、四四~四七週齢時の六四・九g以降は横ばいからやや減少で推移し、マリアは産卵全期にわたり、他銘柄に比べて低く推移しました。
日産卵量、飼料要求率については、銘柄間に統計的な差はありませんでした。
飼料摂取量はジュリアとEXが多く、マリアが少なく(P<0.05)、ジュリアとマリアの差は約四gでした。
生存率はライト、ソニアが九六・九%で、最も低かったEXとの差は四・二%でした。
(三)成鶏期(卵質)
卵質検査は三三、四四、五四、六五、七七週齢で計五回実施し、その平均で示しました。
ハウユニットは、全銘柄の平均八四以上と良好で、特にマリアは八七・二でソニア、ボリスに比べて優れていました(P<0.05)
卵殻強度は、ジュリアが四・四四kg/cm2で、EX、マリア、ソニア、ボリスより統計的に有意に優れていました(P<0.05)。図4に示した卵殻強度の推移では、産卵全期間にわたって、ジュリアの卵殻強度が優れていました。
卵黄重比は、ライトが二八・〇%で、最も少なかったボリスの 二四・五%に比べて三・五%の有意な差がありました(P<0.05)、
肉斑は、白玉鶏の四銘柄では、E
X一%、その他は〇%でした。一方、赤玉鶏のボリスは十二%と最も多く認められました(P<0.05)。
(四)成鶏期(規格卵比率)
規格卵比率では、平均卵重の軽い白玉のライト、マリア、中間色のソニアでM吸以下の比率が六六%前後と多く、逆に平均卵重の重いジュリア、EX、ボリスではL級以上の比率が五○%前後と高い傾向がありました。
産卵期後半に卵重が重かったジュリアは、LL以上の比率が最も高く、L~MSのパック卵比率は、産卵期後半に低く推移し(図5)、平均でも最も低い値でした(P<0.05)。
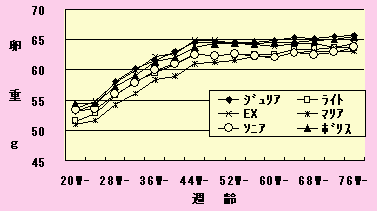
図2 平均卵重(20~80週齢) | 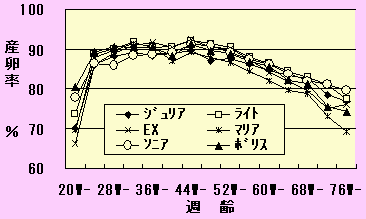
図1 産卵率(20~80週齢) |
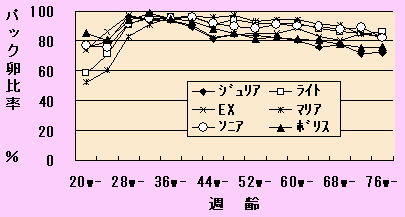
図5 パック卵比率(20~80週齢) | 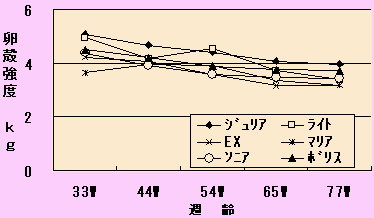
図4 卵殻強度(33~77週齢) | 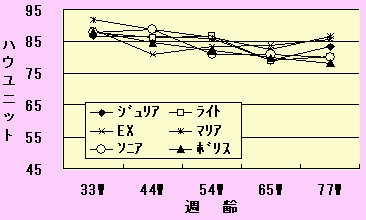
図3 ハウユニット(33~77週齢) |
(五)収益性
収益性は生産卵量×卵価―(ヒナ代+育成飼料費+成鶏飼料摂取量×飼料価格)の式とし、新聞相場の全農の規格卵価及び東京鶏卵事業協同組合の非規格卵価の月平均卵価を用いて計算しました。この結果、非規格卵収益、規格卵収益ともに、ボリス∨ライト∨ジュリア∨EX∨ソニア∨マリアの順となり、特にマリアは規格卵収益で他の五銘柄に比べて統計的に有意な差が認められました(P<0.05)。
なお、二○年二月え付け鶏の経済検定を、白玉鶏のジュリア、ジュリアライト、B四○○、マリア、ピンク玉鶏のソニア及び赤玉鶏のボリスブラウン(ボリス)の六銘柄について、現在実施しており、成績がまとまり次第、ご報告させていただく予定です。
(畜産技術センター
企画経営部 引地宏二)
この記事の詳細は、神奈川県畜産技術センターHP
研究情報&技術情報


昨年暮れ、平成二十年十二月一日から五日までの五日間、(社)全国家畜畜産物衛生指導協会事業による平成二十年度生産衛生技術等向上研修(受精卵移植技術:ET技術)が、福島県西白河に在る(独)家畜改良センターにおいて開催され、県畜産会のご配慮により受講してきました。
研修の内容は、牛受精卵の採卵から移植までの一連の講義と、実際に牛を使った実習という、現場に則し
た研修でした.研修生は十一名。なんと私以外は、すべてNOSAIの獣医師(日常的に牛の診療を行い、直腸検査や人工授精バッチリ!の先生)だったのです。
そんな中、牛の診療、特に繁殖関係をやっているわけではなく、人工授精など全くやった経験も無い私が、ETに挑戦です。家保で牛を担当するようになり、採卵でアシスタントの経験はあるものの、採卵実施者としての経験がないうえ、背が低く手も短い私にとって、実習はついていくだけでやっとの研修でした(全身糞まみれ&筋肉痛に・・)。
講師や研修生の先生方の温かい励ましや情報交換により、充実した研修になりました。しかし、この研修を受けたからといって、即、採卵技術者としての経験値が急上昇したというわけでは到底ありません。
今回、研修を受けるにあたり、ご理解、ご協力いただいた方々に感謝するとともに、今後、この経験を生かせるよう、技術を磨き神奈川県のET普及にお役に立てればと考えています。
(県央家畜保健衛生所 三木桐美)

採蜜時期が近づいていますミツ
バチの衛生管理は大丈夫ですか
|
毎年春に実施するふそ病検査時にダニ対策を聞かれることがあります。そこで、バロア病対策について紹介します。この病気はミツバチへギイタダニの寄生による病気です。このダニは主に蜂児に寄生し、産卵及び繁殖の場も育児巣房内です。蜂児のいない越冬きは成蜂に寄生して越冬します。このダニは蜂と蜂の直接接触により伝播します。防除法は次の三つの方法を紹介します。(一)生物学的防除:有蓋雄蜂巣板を繰り返し取り除く方法があります。このダニは雄鉢の蜂児を好む性質があるため、巣箱内に雄蜂用の巣板を導入し、全体が有蓋蜂児となったところで取り出す方法です。また、産卵調
節器を用いて、女王蜂の産卵を3枚の巣板に限定し、その巣板全体が有蓋蜂児となったところで取り出す方法もあります。この方法はハチミツ等への残留及び耐性の心配がないため、採蜜期にダニの寄生率を低く抑えるのに有効です。(二)科学薬剤による防除:薬剤はフルバリネート製剤が使われています。このダニは巣房内に侵入し増殖し、若バチが出房するときに寄生しています。産卵から出房までに約二一日(三週間)を要するため、薬剤の使用期間は短くても効果が得られません。また、巣箱及び巣箱周辺に長期間放置するとダニに耐性ができ、効果が認められなくなるので、使用期間(四~六週間)は厳守して下さい。また、蜂児が増える時期は防除効果が高いですが、採蜜時期等は使用できないため注意して下さい。(三)弱科学薬剤による防除:乳酸、蟻酸等があります。乳酸は十五%乳酸溶液を作り、巣板の片面あたり八mlをスプレーします。この方法は蜂児には有害であるため、主に冬期に行います。蟻酸は一般に六〇~八〇%に希釈した液二〇mlをペーパータオルに染みこませ、巣板の末において蒸散させる方法が用いられています。二回の処理で効果が高くなりますが、外気温が低いと効果が出にくいです。採蜜期後の蟻酸による長期処理は越冬蜂建勢に悪影響が出るため、この時期は短期処理とすることが望ましいです。秋の寄生率の状況を見て、必要であれば越冬用の給餌が終了した後で長期処理をします。蟻酸は腐食性が強く、皮膚についた場合やけどをする可能性があり、また、用量や用法を誤るとミツバチにも損失がでるため十分注意して下さい。
以上、防除法を紹介しましたが、寄生率の状況及び防除時期に合わせて蜂場全体として対策をとって下さい。
(足柄家畜保健衛生所 荒木悦子)


2月は、大野山牧場にとって一年中でもっとも寒い時です。作業終了後の水道管凍結防止の水抜きはもちろんのこと、昼間でも厩舎周辺の日の当らない場所のコンクリートは完全に冷え切っており、流した水がすぐにカチカチに凍りつき長靴で牛舎周辺を歩き回る際注意しないとスッテンコロリンしかねませんし、氷の上を作業車で通るのも滑ってびっくりするものです。牛舎パドックの糞も凍って固まってしまい、長靴で蹴っ飛ばしたり角スコでたたいたくらいではびくともせず逆に躓いて転びそうです。でも、牛達は、この寒さが体にちょうど合うらしく、咳もせず鼻水も出さず元気にやっています。このような中、唯一暖をとれる憩いの場所が牛のお尻(直腸)の中です。本当に牛のお尻の中は暖かく手を入れていると天国で、体ごととは言いませんが、手だけでなく足も入れたいくらいです。
2月は大野山の冬の風物詩となっている「火入れ」を行います。「火入れ」とは、放牧地の雑草を退治し春先からの放牧に適した牧草の生育を促すための草地改良と小型ピロプラズマ病を媒介するダニの駆除を目的に例年この時期に行っている大事な作業です。立ち枯れている雑草を刈り払いそれに火をつけ焼き払うという単純な野焼き作業ですが、火を使うため、風向き等を考慮し職員一同呼吸を合わせ安全を確認しながら火を点けていかなければなりません。側で見ていると火遊びをしているようで面白そうに見えますが、職員は、煙に燻されながら大変緊張を強いられる厳しい作業です。
先日、新聞に「着信★うし♪」(3等の乳牛の歌声による携帯の着うた)の記事が載っておりました。丑年にあやかったユニークなアイディア商品です。大野山でも生産者や消費者と一緒に腹の底からホットになる明るい話題がないかと考えてい
ます。皆様のグッドアイディアを大野山へお寄せ下さい。
(大野山乳牛育成牧場長)